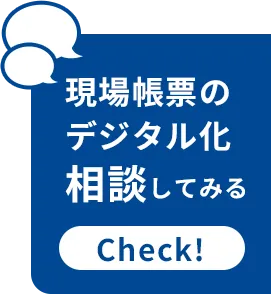生産効率とは?計算式や生産効率を上げる方法をわかりやすく解説
生産効率は、製造現場の運用状況を客観的に評価するうえで欠かせない指標です。生産活動にかかる労力やコストを最小限に抑えながら、どれだけ計画通りの成果を出せているかを可視化すれば、業務改善や現場改善の方向性を明確にできます。本記事では、生産効率の定義や計算方法、改善のポイントを解説するとともに、実際の成功事例やデジタルツールの活用による改善活動のヒントをご紹介します。
目次
生産効率とは?
製造の現場では、ムダを抑えながら作業を進めることが欠かせません。その状況を数値で把握できるのが「生産効率」です。ここでは、生産効率の考え方と、よく似た言葉である生産性との違いをご紹介します。
生産効率とは
生産効率とは、製造現場での生産活動において、「必要な投入(労働力や時間、コスト)」に対して、「実際にどれだけの投入で運用できたか」を示す指標です。例えば、製品を完成させるのに本来必要とされる人数や工数、時間内で作業が完了していれば、生産効率が高いと評価されます。
反対に、ムリ・ムダ・ムラが多く、予定より余計な投入が発生した場合には、生産効率が下がっていると判断できるでしょう。生産効率を数値で確認することは、改善活動や工程管理の見直しに欠かせません。
生産効率と生産性の違い
生産効率と生産性は混同されがちですが、それぞれ異なる意味を持つ指標です。生産効率は、決められた時間や人員、設備などを過不足なく使い、ムダなく計画通りに生産できているかどうかを表します。一方の生産性は、投入した人や時間、原材料などの資源に対して、どれだけの成果を得られたかを示すものです。
生産性は「産出量÷投入量」の計算式で算出され、限られた人員や時間で多くの製品を作れていれば、高いと評価されます。ただし、生産性と生産効率は必ずしも比例するとは限りません。生産性を上げようとして過剰に作りすぎると在庫が膨らみ、余分な作業や管理工数が発生する場合があり、生産効率の低下にもつながるでしょう。
生産効率の基本的な計算式
生産効率を評価する際には、「生産に必要なコスト」と「実際に投入されたコスト」の比率を用います。計算式は以下のとおりです。
計算式:「生産に必要なコスト÷実際に投入されたコスト」
「生産に必要なコスト」には、作業員の数や作業にかかった時間、設備稼働時間など、作業に関わるさまざまな要素を含みます。また、「実際に投入されたコスト」とは、実際にかかった労働力や時間、設備稼働時間などです。
計算式では、計画通りの投入で作業を終えられていれば「1.0(=100%)」となり、1.0を上回る場合は生産効率が高い、下回れば生産効率が低いと判断されます。
例えば、ある工程において「作業員2人で1時間あれば完成できる」と計画されていたとします。このケースでは、計画上の投入コストは「2人×1時間=2」です。実際には3人で1時間かかっていた場合、投入コストは「3人×1時間=3」となります。
このときの生産効率は以下のように計算できます。
生産効率 = 2 ÷ 3 = 約0.67(67%)
つまり、計画よりも人員を多く投入してしまい、約33%の効率低下があったと判断されます。このように、生産効率は数値として把握できるため、改善点を見つけやすいのです。
生産効率を高めるメリット
生産効率を改善すると、現場の作業負担が軽減されるだけでなく、業務全体にさまざまな好影響が及びます。ここでは、3つの代表的なメリットについて見ていきましょう。
コスト削減
生産効率が高まると、業務にかかる時間や人員が最適化されます。作業のムリやムダが減ると、労働生産性の向上にもつながり、限られた資源の有効活用が可能です。
また、業務フローの改善や自動化により、人件費や設備費などの経費を抑えられ、全体のコストダウンが実現できるでしょう。
品質の安定
効率的な体制を整えれば、作業の標準化が進み、ミスの発生も抑えられます。製品やサービスの品質にバラつきが出にくくなり、全体の品質管理が安定するでしょう。
また、作業員のスキルに依存しない体制であれば、担当者が変わっても品質を維持しやすくなります。
利益の増加
生産効率が高まれば、同じ設備や人員を使っても、より多くの成果を上げられ、売上や利益の拡大につながります。限られた資源を無駄なく活用でき、収益構造が安定し、事業の成長にもつながるでしょう。
利益が出やすい体制が整えば、新しい設備への投資やDXの推進、AI技術の導入といった次の展開にも踏み出しやすくなり、企業の競争力をさらに高められます。
生産効率が悪い主な原因
生産効率が思うように上がらない背景には、現場の体制や業務フローに問題が潜んでいるケースも少なくありません。ここでは、よく見られる3つの原因をご紹介します。
人手不足
労働人口の減少や人材確保の難しさにより、現場の人員不足が続くと、1人あたりの作業負担が増えるでしょう。作業ペースが落ちると、全体の効率にも悪影響が及びます。
また、限られた人員で多くの業務を担う状態では、長時間労働やマルチタスクが常態化しやすく、集中力の低下やモチベーションの維持にも支障をきたしかねません。このような状況では、作業ミスやヒューマンエラーが増加し、品質や納期の安定性にまで影響する恐れがあります。
業務の標準化不足
作業手順やマニュアルが整っていない職場では、担当者ごとにやり方が異なり、工程全体にムラが生じやすくなります。作業スピードや品質に差が出るだけでなく、ミスや手戻りの発生率も高まり、生産効率が落ち込む原因となるでしょう。
さらに、特定の人しかできない業務が多い場合も、担当者が不在の際に作業が滞り、効率が著しく低下する可能性も否定できません。
部門間の連携不足
製造・調達・営業などの各部門で、情報共有や連携がうまくいかない状態が続くと、業務の進行に支障をきたします。工程の遅れや手戻りといった問題も生じやすくなり、生産効率の大幅な低下につながるでしょう。
生産効率を上げるには?
業務全体の流れを見直し、ボトルネックを解消することが、生産効率の改善につながる第一歩です。ここでは、現場で実行しやすい4つのポイントをご紹介します。
5Sを徹底する
職場の整理・整頓・清掃・清潔・しつけ、いわゆる「5S」の徹底は、作業効率と品質の安定化に直結する取り組みです。5Sを実現し、必要な道具がすぐに見つかる環境を保てれば、探し物にかかる時間や無駄な動作が削減され、業務全体のスピードも向上します。清掃と点検を組み合わせれば、不具合の早期発見にもつながり、トラブルの未然防止にも有効です。
手順を標準化する
作業手順やマニュアルを統一すれば、誰が作業しても一定の品質とスピードを維持できる体制が整います。手順に迷う場面が減るため、ミスや作業のばらつきが抑えられ、生産の安定にもつながるでしょう。新人への教育もスムーズになり、育成にかかる負担の軽減が図れる点も大きなメリットです。
部門間の連携を強化する
製造・調達・営業などの各部門がスムーズに連携するには、情報共有できる仕組みの構築が欠かせません。定期的なミーティングやITツールの活用により、進捗や課題をリアルタイムで共有できるようにすれば、工程の遅延や手戻りのリスクを未然に防げるでしょう。連携が円滑になれば、業務全体の効率も高まります。
自動化や省力化を推進する
人手に頼っている組立や検査などは、自動化によって、人手不足の解消や作業精度の向上につながります。加えて、クラウド型のシステムを導入すれば、生産管理や事務作業の負担も軽減され、全体の業務効率を押し上げる効果が期待できるでしょう。
ツールの導入で生産効率が向上した事例
デジタルツールの導入は、現場業務に潜むムダを可視化し、生産効率の向上に直結する取り組みです。ここでは、帳票業務のデジタル化によって、実際に業務改善を実現した企業の事例をご紹介します。
広大な造船工場で業務効率UPとコスト削減につながった事例
名村造船所では、広大な構内で行われるガス漏れパトロールや資産管理などの現場作業において、写真撮影や手書きメモ、紙帳票を併用した情報伝達が、多くの手間と時間を要していました。さらに、紙の帳票や回覧物の管理が煩雑で、情報の分断やタイムラグの発生、過去の記録を探す際の手間が、業務の効率を下げる要因となっていたのです。報告書や写真の管理も個別で行われており、情報の一元化が進まず、現場と管理部門の間でフィードバックを迅速に行うのが難しい状況でした。
こうした課題を受け、「i-Reporter」を導入した結果、帳票作成や情報伝達の手段がデジタル化され、現場作業にかかる時間が大幅に削減されました。具体的には、1日あたり約1時間の作業時間短縮と、年間約80万円弱のコスト削減を実現しています。
写真や複数の情報を1枚の帳票にまとめて管理できるようになり、資産の把握や報告業務の精度とスピードも向上。さらに、デジタル回覧によって、従来発生していたタイムラグが解消され、帳票の進捗や滞留状況を即座に確認できる環境が整い、現場対応と管理業務の効率化が進みました。
製造ラインの記録の効率化事例
古河電気工業株式会社では、製造現場における作業日誌や設備点検記録をすべて紙で運用しており、帳票の年間使用枚数は約15,000枚にのぼっていました。ファイリングには月200分以上を費やし、保管スペースの確保も悩みの種となっていたのです。また、現場で品質トラブルが発生した際には、従業員が紙の帳票を手作業で整理する必要があり、原因特定までに数日かかるケースも珍しくありませんでした。
「i-Reporter」の導入によって帳票のデジタル化が進み、ファイリング作業の負担はゼロになりました。紙帳票を保管していたスペースも不要となり、物理的な管理工数の削減にもつながっています。
さらに、検索機能の活用により、以前は1帳票あたり20分を要していた確認作業が、現在では5分以内で完了できるようになりました。帳票の即時活用が可能になったことで、トラブル対応のスピードも向上し、業務全体の効率化と品質管理の強化を実現しています。
帳票のデジタル化で生産効率を改善する「i-Reporter」
生産効率を高めるには、作業のムダを把握し、業務の段取りや流れを改善しなければなりません。なかでも、帳票の作成・記録・管理といった、日常業務に潜む非効率は見落とされがちですが、放置すれば手間や時間のロスにつながります。
「i-Reporter」は、紙帳票のレイアウトをそのままデジタル化できる現場帳票システムで、製造業を中心に多くの企業で導入されています。タブレット上で簡単に記録でき、現場に無理なく定着し、帳票業務全体の効率化が可能です。さらに、入力データを活用すれば、報告や分析といった後工程の負担も軽減されます。
生産現場の情報管理を見直し、作業効率と品質の両立を図るには、紙ベースの帳票からの脱却が有効です。業務の流れに合わせて柔軟に運用できる「i-Reporter」を活用し、生産効率の向上を目指してみてはいかがでしょうか。