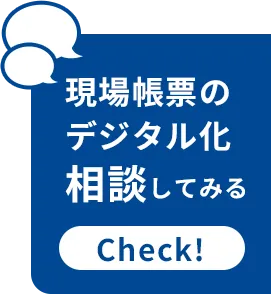目次
在庫管理や工程管理の効率化が求められる現場において、RFID(Radio Frequency Identification)は、欠かせない技術の一つとなっています。RFIDは、電波を用いた非接触のデータ通信により、商品や部品、人物などの情報を即座に読み取る自動認識技術です。従来のバーコードや2次元コードとは異なり、視認や接触を必要とせず、多数のタグを一括でスキャンできる点が大きな特長です。本記事では、RFIDの仕組み・特徴や実際の活用事例を踏まえ、物流・小売業・製造業での導入メリットや注意点をわかりやすく解説します。
RFIDとは?
RFIDとは、「Radio Frequency Identification」の略で、無線通信を活用し、非接触でデータの読み書きを行う自動認識技術です。RFタグ(ICタグ)と電波を通じて情報のやり取りを行うため、バーコードのような目視確認や、ハンディターミナルを利用したスキャン操作が不要で、モノや人の識別・管理を効率化できます。
RFIDは主に、「RFタグ(ICタグ)」「リーダー(読み取り機)」「情報処理システム」の3つで構成されており、それぞれが連携してデータの取得と管理を行います。
RFIDの仕組み
1.リーダー(読み取り機)が電波や磁界を発信し、RFタグに信号を送信する
2.RFタグのアンテナが受信し、内蔵された制御回路やメモリが動作して必要な処理を行う
3.RFタグが内部のデータを電波や磁界に乗せてリーダーに送信する
4.リーダーが信号化されたデータを受信し、情報を取得する
また、RFタグは、電源の有無によって3つのタイプに分かれます。
・パッシブタグ:別名「パッシブ型」「パッシブタイプ」とも呼ばれ、バッテリーを持たず、安価で大量運用に適しており、電子マネーをはじめ、アパレルや物流現場で広く使われている。
・セミアクティブタグ:別名「セミパッシブタグ」とも呼ばれ、読み取り時にだけバッテリーで動作するため、通信距離に優れ、省電力であることが特長。
・アクティブタグ:別名「アクティブ型」とも呼ばれ、常時内蔵した電池で駆動し、長距離通信やセンサー連携が可能。一方で、価格やサイズが大きくなる傾向がある。
RFIDの活用例
RFIDがどのように活用されているのか、導入事例をご紹介します。
・交通系ICカード:
ICチップに記録された残高・履歴情報で改札やチャージ処理を自動化
・在庫管理:
商品にRFIDタグを貼付し、RFIDリーダライタで在庫確認や棚卸しなどの商品管理を効率的に実施
・物流:
荷物や製品にRFIDタグを貼付し、荷物の追跡やトレーサビリティの向上、検品作業の自動化に活用
・アパレル業界:
商品に電子タグを貼付し、セルフレジ化や盗難防止・追跡、リアルタイムの在庫管理や棚卸に活用
・その他:
専用タグを用いて、図書館の蔵書管理や工具・医療機器の所在確認、入退場管理や動物の管理などに活用
RFIDは、非接触かつ高速に情報を読み取る特性を活かして、ITシステムやIoTとの連携や、AIによる分析にも活用されています。現場の業務改善や自動化を支えるソリューションとして広く普及しており、今後もさまざまな業界への導入が進んでいくでしょう。
RFIDとバーコードや二次元コードとの違い
RFIDは、視認性や通信範囲などの点で、従来のバーコードや二次元コードとは大きく異なり、近年では技術的も急速に進化しています。それぞれの特徴を比較してみましょう。
特徴 RFID バーコード 二次元コード
読み取り方式 電波(非接触) 光(スキャン) 光(スキャン)
視認の必要性 不要(箱の中や裏面でも読み取り可) 必要(コードが見える必要あり) 必要(コードが見える必要あり)
読み取り距離 数メートル 数十センチ 数十センチ
情報の書き換え 可能
(タグの種類による) 不可
(印刷内容固定) 不可
(印刷内容固定)
データ容量 数千文字(タグにより異なる) 数十文字 数千文字
耐久性 高い
(衝撃や汚れに強い) 紙の場合は弱い 紙・印刷面が傷つくと読取不可
コスト 高め 低い 低い
RFIDは、バーコードよりも通信距離が長い点や視認が難しい場所でも使用できる点、ラベルが貼られた多数のタグを同時に読み取れる点で大きな優位性を持ちます。一方、バーコードや二次元コードは導入コストが低いため、手軽に導入しやすい点がメリットです。目的や用途、コストや導入環境に応じた使い分けが、効率的な運用には欠かせません。
「i-Repo Scanなら、複数のバーコードを連続で画面に映しながら、一括&連続で読み取りが可能です。種類が混在していても、必要なバーコードだけを選んで読み取れるので、定期的な棚卸やピッキング作業のスピードアップにつながります。
在庫・工程管理にRFIDを導入するメリット
在庫管理や工程管理の現場では、作業の正確さと処理のスピードが重要です。ここでは、RFIDの導入によって、在庫管理や工程管理の課題をどのように解決できるのか、具体的なメリットをご紹介します。
作業効率の向上
RFIDの導入によって、作業効率や業務効率が大きく向上します。複数のタグを非接触で一括かつ高速に読み取れるため、商品や製品の棚卸し、工程の進捗確認や在庫管理といった、作業の手間と時間の大幅な削減が可能です。また、箱の中や高所、手の届かない場所にある商品も開封せずにスキャンできるため、作業者の負担も軽減できます。
●正確性の向上
RFIDを導入することで、記録されるデータの正確性が大きく向上します。製造工程ごとの進捗状況や在庫数をリアルタイムで更新できるため、手作業による記録ミスや転記ミス、確認漏れといったヒューマンエラーを防ぐことが可能です。これにより、業務品質の安定化と信頼性の向上が期待できます。
●所在管理・トレーサビリティの強化
RFIDの導入は、所在管理やトレーサビリティの強化にも役立ちます。RFIDを使えば、物品の現在地や移動の履歴、工程ごとの進捗状況といった情報を、リアルタイムに把握することが可能です。これらの情報は一元的に管理できるため、紛失や行方不明のリスクを減らし、不良品の発生原因を特定しやすくなるなど、品質管理の強化に大きく貢献します。
RFIDのデメリット
利便性の高いRFIDですが、導入にあたってはコストや運用環境に関する課題も存在します。
導入・運用コストが高い
RFIDのデメリットの一つが、導入・運用コストの高さです。RFIDを導入する際には、RFIDタグやリーダー機器、システムの開発費用といった初期投資が必要で、価格は高額になる傾向があります。また、導入後も保守点検やバッテリーの交換、ソフトウェアの更新など、メンテナンスや運用コストが継続的に発生するため、長期的な視点でのコスト管理が求められます。
環境によっては不向き
使用環境によっては、RFIDの性能が十分に発揮されず、運用に支障をきたす可能性がある点もデメリットです。特に、金属や水分の多い環境では、電波が影響を受けやすく、読み取り精度が低下するリスクがあります。そのため、タグの取り付け位置や、使用する通信方式や周波数帯(LF(135KHz)・HF(13.56MHz)・UHF(860~960MHz)・マイクロ波帯(2.45GHz))の選定には注意が必要です。
RFIDとは何かを知ったうえで、i-Reporterと連携して業務改善を実現
RFIDとは、電波や電磁誘導方式を使って非接触で情報を読み書きできる技術で、在庫や工程の管理に役立ちます。物流管理や製造管理の現場では、棚卸しや検品、進捗確認といった作業の自動化や効率化に貢献し、業務のスピードと正確性を大きく高められる点が特長です。
現場帳票システム「i-Reporter」は、紙の帳票をデジタル化するだけでなく、RFIDリーダーとの連携により、現場データのリアルタイム収集と一元管理が可能です。連携することで、タグ情報を自動的に帳票に反映させたり、作業状況を即時に可視化できたりするため、業務の進捗管理やミスの削減に大きく貢献します。
RFIDシステムの詳細を正しく理解し、「i-Reporter」と連携させることで、業務の見える化やDX化、ヒューマンエラーの削減やトレーサビリティの強化など、多くの課題解決を実現できますので、ぜひ導入をご検討ください。