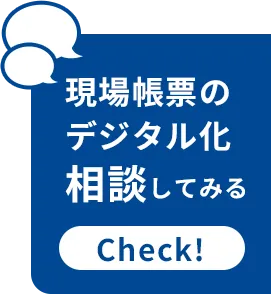計測器の校正とは?実施の方法やタイミング、ISO9001との関係を解説
製造現場や研究開発の現場では、製品や試験結果の精度を左右する計測器が不可欠な存在です。しかし、どれほど高性能な計測機器であっても、経年や使用状況により徐々に誤差が生じる可能性があります。誤差を検知し、適正な状態に保つために行うのが「校正」です。校正は、製品の品質保証や信頼性の向上、さらには国際的な基準への適合といった観点からも重要な業務です。本記事では、計測器の校正が必要とされる背景や実施方法、ISO9001との関係についてわかりやすく解説します。
目次
計測器の校正とは?
計測器の校正とは、使用している計測器や測定機器が、正確な数値を示しているかを確認する作業です。校正は、高精度な標準計測器との比較測定を通じて行われ、誤差の有無を調べたうえで補正や調整を施します。この一連の校正作業によって、測定結果の精度や信頼性を保てるのです。
計測器の校正が必要な理由
校正は、品質管理や試験結果の信頼性を確保するうえで欠かせません。経年劣化や部品摩耗、温湿度などの測定環境の変化により、計測器の誤差は徐々に蓄積されます。
このような誤差を放置すると、測定値の不確かさが増し、製品不良や安全リスクを招き、企業の信用や製品の評価にも悪影響を及ぼす恐れがあります。
計測器の校正を行うタイミング
計量法で定められた「特定計量器」は、定期的な検査が義務化されています。一方、その他の一般的な計測器には、明確な法律上の周期は設けられておらず、製造元が推奨する周期に従うのが通例です。
例えば、多くのメーカーでは、「1年ごと」などの推奨校正周期を設けています。ただし、使用頻度や環境、求められる測定精度によっては、より短いスパンでの校正が必要となる場合もあり、適切な校正周期の設定が必要です。
ISO9001などの品質マネジメントシステムでは、測定機器の定期的な校正とトレーサビリティの確保が要求事項として明示されています。トレーサビリティとは、測定器がどの基準に基づいて校正されたかをたどれる状態を指し、製品の信頼性や監査対応にも直結する要素です。
【計測器の校正を行うタイミングの例】
・定期的(半年~1年に1回が目安)
・測定器のメンテナンス時
・使用前・使用後
・経年劣化が疑われる場合
・測定値に異常や不具合がある場合
・測定環境が大きく変わった場合
計測器の校正とISO9001との関係
品質マネジメント規格であるISO9001では、「監視機器及び測定機器の管理」が要求事項の一つとして規定されています。計測器の校正も対象であり、企業は具体的な管理方法を整備しなければなりません。
測定機器の校正に関する主な管理基準は次のとおりです。
・定められた間隔または使用開始前の校正の実施
測定機器は、一定の周期または使用開始前の校正の実施が求められます。定期的な校正によって、測定値の精度や信頼性を維持し、不確かさを抑えることが可能です。
・国際または国家計量標準にトレーサブルな計量標準の使用
校正に用いる基準器は、IECなどの国際標準や国家計量標準とトレーサビリティが確保されたものでなければなりません。基準との整合性を保つと、校正結果の信頼性が保証されます。
・校正記録の保持
校正証明書や成績書、トレーサビリティ体系図などの記録は、品質監査や顧客からの問い合わせ、製品不良発生時の原因調査に備えて、適切に保管しておく必要があります。
測定機器の校正業務を計画的に実施し、記録を整備すれば、ISO9001の要求に応じた品質管理体制の構築が可能です。校正の管理は、製品やサービスの信頼性を支える基盤となります。
計測器の校正を実施する方法
計測器の校正は、自社で行う方法と外部に委託する方法に大きく分けられます。どちらの方法にも特性があり、導入環境や求められる精度、社内のリソース状況によって適切な手段を選ばなくてはなりません。それぞれの実施方法と、メリット・デメリットについて確認しましょう。
自社で計測器の校正を実施する
自社で校正を行う場合は、まず高精度な標準器(リファレンス)を準備し、計測器と比較して誤差を測定します。作業環境には温度や湿度が安定した恒温室が適しており、校正手順や記録の整備も欠かせません。担当者は十分な教育と訓練を受け、校正作業を正しく実施できる体制の構築が求められます。
・社内で計測器の校正を行うメリット
計測器の校正を社内で実施する場合、外部への委託費用が発生せず、コストを抑えられます。また、機器を外部に持ち出す必要がなく、移動中の破損リスクやダウンタイムも最小限に抑えられるでしょう。
さらに、自社の業務スケジュールに合わせて柔軟に対応できることもメリットの一つで、現場の状況に応じたタイミングで校正作業を進められます。
・社内で計測器の校正を行うデメリット
社内で校正を行うには、高精度な標準器や恒温室などの設備を整える必要があります。校正業務を担当する従業員には、事前の教育や実務訓練を行い、手順書の作成や管理体制の整備も並行して進めなければなりません。
また、トレーサビリティや第三者証明の信頼性については、外部の校正機関と比べて不十分と見なされる場合があり、評価の面で不利になる可能性もあるでしょう。品質マネジメントに関連する審査や監査では、このような体制の不備について指摘を受ける恐れがあるため、記録や管理方法の整備が求められます。
外部に委託する
外部に計測器の校正を委託する場合は、メーカーやJCSS認定を受けた校正専門業者などへの依頼が一般的です。校正証明書や成績書を発行してもらえば、トレーサビリティが確保されます。
・外部に計測器の校正を委託するメリット
外部に校正を委託すれば、校正証明書や成績書が発行され、監査や顧客からの要求に対応しやすくなるでしょう。加えて、高度な技術や設備を備えた専門業者が対応するため、測定精度や作業の信頼性も高まります。
また、社内で校正体制を構築する必要がなく、教育や運用にかかるリソースを抑えられる点も大きなメリットです。
・外部に計測器の校正を委託するデメリット
外部に委託する場合は、校正のたびに費用が発生します。また、校正に出している期間は計測器が使用できず、業務に支障が出る恐れもあるでしょう。
さらに、機器の発送や返送にかかる手続きや管理にも時間と労力が必要です。
計測器の校正についてよくある疑問
計測器の校正には、専門的な知識や判断が欠かせません。事前に想定される疑問を把握しておくと、スムーズな対応につながります。
校正証明書や成績書はなぜ必要?
校正証明書や成績書は、測定値の正確さや信頼性を対外的に証明し、トレーサビリティを確保するうえで欠かせません。実施した校正が、国際標準や国家標準にトレーサブルであることを示す情報が記載されており、監査や取引先から提出を求められた場合にも対応しやすくなります。
校正事業者に校正を依頼した場合、一般的には校正証明書や校正成績書、トレーサビリティ体系図といった文書が発行されます。
計測器の校正はどこで行うべき?
計測器や試験器などの精密機器は、使用目的や要求される精度によって、校正の実施方法は異なります。トレーサビリティや高い測定精度が求められる場合は、JCSS認定校正や一般校正など、校正サービスを専門に行っている会社へ依頼するのが一般的です。
一方、用途が限定される機器や簡易的な確認を目的とした場合には、社内でも校正を行えます。ただし、社内で対応する際には、使用する標準器の信頼性や記録の保管方法にも注意が必要です。
計測器の校正時に異常が見つかったらどうする?
校正の過程で、測定値のずれや動作の不具合が確認されるケースもあるでしょう。異常や故障が判明した際には、まず原因を特定し、必要に応じて修理を行ったうえで、改めて校正を実施する必要があります。
なお、校正を依頼した機関が修理に対応していない場合は、計測器メーカーや専門の修理業者に依頼します。再校正を含めた一連の対応が必要となり、スケジュールや費用も考慮しなければなりません。
計測器の校正業務を効率化するなら「i-Reporter」の導入が有効
計測器の校正は、製品品質や安全を守るうえで欠かせない業務です。正確な測定値を維持し続けるには、定期的な校正を行い、国際標準や国家標準とのトレーサビリティを確保しなければなりません。
校正業務を効率的に管理したい場合には、現場帳票システム「i-Reporter」の活用が効果的です。校正記録や使用履歴をデジタルで正確に残せるため、紙帳票の手書きミスや転記漏れといったリスクを軽減できます。さらに、記録データは品質管理や監査対応にも活用でき、万が一のトラブル時にもスムーズな原因究明につながります。
校正とトレーサビリティ管理を省力化しつつ、現場の信頼性を高めたい現場にとって、「i-Reporter」は有効な導入ツールといえるでしょう。導入方法や機能の詳細については、PDFの案内資料をご覧いただくか、お気軽に問合せください。