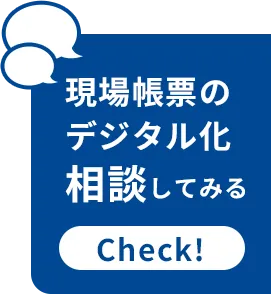目次
製造業の現場やオフィス業務では、仕事や作業を始める前の段取りが、成果や納期に大きな影響を及ぼします。現場では、「準備に時間がかかりすぎる」「機械の停止時間が長い」といった悩みを抱えるケースも少なくありません。段取りとは、物事を進める際の流れや手順を事前に考え、必要な準備を整える行為を指します。特に製造現場では、QCD(品質・コスト・納期)をバランスよく管理するうえで、欠かせない取り組みです。段取りを効率的に行えば、生産性向上や納期短縮、品質の安定につながり、企業全体の競争力強化にも直結します。本記事では、段取り時間を短縮するメリットや具体的な進め方から、成功のポイントまでを詳しく解説します。
段取り時間を短縮するメリット
段取りの効率化は、生産現場やオフィス業務における改善活動の大きな柱となります。段取りにかかる時間を短縮すれば、業務の流れがスムーズになり、作業者の負担軽減や生産性向上など、幅広い効果が期待できるからです。以下から、段取り時間を短縮する主なメリットをご紹介します。
業務の効率や生産性が向上する
必要な道具や材料があらかじめ整理整頓されていれば、作業開始や工程の切り替えに余計な時間をかけずに進められます。さらに、作業手順や役割分担を明確にすれば、無駄な移動や探し物の時間を削減でき、属人化のリスクも下がるでしょう。段取りや算段を意識すれば、限られた作業時間の中でも生産能力を高めやすくなり、結果的に生産性向上につながります。
納期遵守率が上がり信頼性が高まる
段取り替えの時間を短縮できれば、生産ラインの停止時間が減り、工程全体がスムーズに流れます。段取りや段替えが納期遅延の発生を防ぎ、取引先への納品を安定させられるため、顧客からの信頼を得やすくなります。納期を守れる体制は、継続的な受注や取引拡大にもつながるでしょう。
コスト削減や品質の安定につながる
段取りを短縮すると、ムダな調整作業を減らし、稼働時間の低下も防げます。段取り時間の短縮によって、生産工程における不要な停止が少なくなれば、人件費やエネルギー費の負担が軽減され、コスト面で効果を得やすくなるでしょう。さらに、段取りを調整する中で、作業を標準化して手順のバラつきを抑えれば、ヒューマンエラーを防止し、不良品や手戻りの減少にも結びつきます。安定した品質を維持できれば、生産管理全体の信頼性も高まります。
段取り時間短縮の進め方
段取り時間を短縮するには、現状の作業や工数を可視化し、ムダを見極めたうえで、工程ごとの改善策を段階的に実施すると効果的です。段取りの仕方を以下のステップに沿って進めれば、現場改善の精度が高まり、持続的な成果につながります。
STEP1.段取り作業の時間を「見える化」する
まずは就業時間のうち、段取りにかかっている割合を明らかにする必要があります。作業ごとにストップウォッチや動画で計測し、所要時間を記録すると効果的です。運搬や製造、在庫管理や品質管理など、どの作業に時間を要しているかを把握できれば、ムダな工程を洗い出しやすくなります。
STEP2.作業を3つに分類する
段取りに含まれる作業を、「内段取り」「外段取り」「ムダな作業」に分けると改善の方向性が見えてきます。
- 内段取り:機械や作業を停止しないと行えない作業(例:部品交換、装置調整、位置決めなど)
- 外段取り:機械を止めずに並行して行える作業(例:工具・資材準備、治具の搬送、後片付けなど)
- ムダな作業:付加価値を生まない作業(例:使用する金型や道具を探す行為)
このように段取りの方法を分類すれば、「どの作業が外段取り化できるか」「どの工程がムダとして排除できるか」といった判断がしやすくなります。段取り時間の短縮を進めるうえで、まずは現状の作業内容を整理し、改善案の優先順位を明確にすることが重要です。
STEP3.ムダな作業をなくし、外段取りを効率化する
分類した結果をもとに、付加価値を生まない作業を徹底的に減らします。5Sの中の2S(整理・整頓)の徹底により、探さない・迷わない環境を整え、作業場の動線を最適化すれば、移動時間の低減が可能です。さらに、手順書やチェックリストを整備し、段取りの手筈や手順といった工程を可視化すれば、作業のバラつきやヒューマンエラーを防止できます。
STEP4.内段取りの一部を外段取り化する
段取りの組み方を確認し、生産を止めずに準備作業できる体制を整えれば、稼働率の低下を防げます。例えば、金型の加熱や調整を事前に別の場所で進めておけば、交換時に時間を取られません。他にも、調整作業の一部を自動化し、人の手間を省く方法も有効です。作業の流れを理解し、先回り準備ができる仕組みを作ると、改善効果が高まります。
STEP5.内段取り・外段取りそれぞれを短縮する
段取りをさらに短縮するには、内段取りと外段取りの両方に対して工夫を加える必要があります。
- 内段取りの短縮例
例1:複数人で作業を分担し、同時に進行する
例2:誰でも同じ手順で進められるよう工程を標準化する
例3:道具配置や設備の機能を見直し、調整にかかる時間を減らす - 外段取りの効率化例
例1:品番ごとに必要な物を箱やトレーでまとめて管理する
例2:加工中に次の部品や治工具を機械の近くに準備する
例3:作業姿勢や配置を最適化し、動作のムダを削減する
内外の作業を並行して改善すれば、段取り替えのスピードを大きく高められます。
段取り時間の短縮を成功させるポイント
段取り時間の短縮を定着させるには、現場の実情に即した段取りやスケジューリングの工夫と、継続的な改善活動が欠かせません。以下のポイントを押さえれば、改善策の実効性が高まり、現場全体の生産性向上につながります。
現場の声を取り入れる
改善活動を進めるうえで、実際に作業を担当する人の声は非常に重要です。日々の業務で感じる小さな不便や工夫を聞き取れば、実現可能な改善案が見えてきます。段取りや根回しを含めた意見交換の場を設けて共有すれば、職場全体で取り組む意識も高まりやすいでしょう。さらに、「生産効率の向上」や「不良削減」といった目的を明確に掲げると、現場から具体的なアイデアが出やすくなります。
マニュアルを作成する
作業の順序や手法が不明確なままでは、人によってやり方が異なり、ムダな動作や時間が生じます。標準化されたマニュアルを作成すれば、段取りと作業の再現性が高まるだけでなく、新人教育にも有効です。さらに、他部署との情報共有もしやすくなり、組織全体の改善につながります。
継続的な見直しをする
設備や製品が変われば、段取りの内容も変化します。改善項目を定期的に見直し、PDCAサイクルを回せば、現場改善の精度が高まります。一度の改善で満足せず、継続的に取り組む姿勢が大切です。
デジタルツールの活用を検討する
現場帳票システムなどのデジタルツールを導入すれば、段取りに関する記録の効率的な管理が可能です。改善前後の数値比較や停止時間の推移を簡単に共有でき、客観的な判断材料を得やすくなります。段階的な導入とフォローアップを行えば、現場に負担をかけずスムーズに運用できるでしょう。
「i-Reporter」で段取り短縮を成功させる現場改善のポイント
段取り時間の短縮は、単に機械の停止時間を減らすだけではありません。生産性や品質、コスト、顧客からの信頼性といった、事業の根幹を支える要素を向上させる重要な取り組みです。現場改善の成果を持続させるには、改善活動の記録やノウハウの共有、効果測定までを一貫して行う必要があります。
こうしたプロセスを加速させる手段として、デジタルツールの活用が有効です。「i-Reporter」は、段取り時間の計測記録や報告書の作成を、デジタルで一元管理できる現場帳票システムです。改善前後の数値比較や、稼働時間の推移を可視化すれば、PDCAサイクルを円滑にし、成果を効率的に活用できます。
「新たなシステムを導入することで、現場にどのような変化が起きるのか具体的に知りたい」「デジタル化が組織に浸透していくイメージをつかみたい」と考えているご担当者様に向けて、ツールの導入段階ごとに社内で起こる変化を解説した資料をご用意しております。段取り短縮の取り組みを定着させるためのヒントとして、ぜひクリックしてダウンロードし、資料をご活用ください。
段階別 現場帳票のデジタル化が進むにつれて起こる社内の変化」の資料請求はこちらから

現場帳票研究所の編集部です!
当ブログは現場帳票電子化ソリューション「i-Reporter」の開発・販売を行う株式会社シムトップスが運営しております。
現場DXの推進に奮闘する皆様のお役に立てるよう、業界情報を定期的に配信致しますので、ぜひ御覧ください!