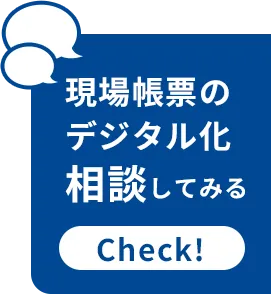BOMとは?主な役割や種類、管理でよくある課題と効率化のポイント
目次
現代の製造業において、製品の生産・管理を効率的に行う上で欠かせないのが、「BOM(部品表)」です。現場や管理の担当者であれば、一度は耳にしたことがあるでしょう。
「BOMが正確ではないから部品が足りない」「設計変更が現場に伝わらない」といった問題は、BOM管理に課題がある場合に発生しがちです。
BOMは、モノづくりの全ての工程をつなぐ「背骨」のような情報であり、その管理方法が企業の生産性を大きく左右します。
本記事では、BOMの基本的な意味から、重要な役割、種類、そして現場でよくある課題と解決のための効率的なポイントまで解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
BOMとは?
BOMは、「Bill of Materials」の略で、日本語では「部品表」や「部品構成表」を指します。
BOMとは、製品を製造する際に必要な部品のリストと、その数量、仕様などをまとめた表または構成表です。
設計、製造、調達、販売、保守など、モノづくりに関わるさまざまな部門が共通で利用します。
製品ライフサイクル全体を支えるBOMは、設計部門が作成した設計情報(図面など)をもとに、部品情報を整理し、共通の情報基盤として機能します。
BOMの役割
BOMを単なる部品リストとして扱っていませんか?BOMは、設計部門から製造部門、調達部門まで各部門を結ぶ「共通言語」のような役割を果たします。
適切な管理・運用により、生産計画の精度向上、製造プロセスの標準化、正確な原価計算といった大きなメリットを享受できるのが特徴です。その具体的な役割と効果を詳しく見ていきましょう。
生産・調達計画の精度向上
BOMは、生産計画を立てる際に必要な部品の種類と数量を正確に把握するための基礎情報となります。製品の生産スケジュールとBOMとの照合により、必要な部品の種類と数量を正確に予測できるでしょう。
結果として、調達部門は適切なタイミングで過不足なく部品を手配でき、部品不足による生産停止や過剰在庫を防げます。納期の遅延を防ぐことができるうえ、部品管理の効率的な運用に直結するのではないでしょうか。
製造プロセスの標準化
BOMは、製造現場において、製品を組み立てる際の正確な作業指示の元となります。
例えば、「どの部品を、どの手順で、いくつ使うか」がBOMに明記されているため、誰が作業しても同じ品質の製品を製造できる体制を構築するための、標準化の基盤となり、品質のバラつきを防ぎ、作業効率も向上するでしょう。
標準化されたプロセスは、新規担当者の教育コスト削減にもつながるというメリットがあります。
正確な原価計算の実現
BOMは、製品に使われる全部品のコストを積み上げることで、正確な製品原価を算出するために不可欠です。
部品ごとの単価や調達コストをBOMに紐づけにより、精度の高い原価計算が可能になり、適切な販売価格の設定や、コストダウンの検討を行うための重要な経営判断材料となります。
データ管理方法によるBOMの分類
現在使用しているBOMは、「サマリ型」と「ストラクチャー型」どちらの形式でしょうか?BOMは、そのデータの表現方法や構造によって、大きく「サマリ型」と「ストラクチャー型」の2つに分類されます。
それぞれの形式は、利用する部門や用途に応じて特徴があるので、使い分けられた部門に合ったBOMの種類を確認しましょう。
サマリ型(レベルフリー型)
サマリ型は、製品を構成する部品や材料をフラットな形式で並べたリストです。
例としては、「製品Aを作るのに部品Bが1つ、部品Cが2つ必要」といった形で、製品全体で必要な数量の一覧化が可能になります。
個々の部品の親子関係や組立順序は考慮されず、製品を構成する全ての品目がリストアップされます。この形式は、総部品数を把握しやすいため、部品手配や在庫管理に向いており、資材部門や購買部門でよく使用されます。シンプルゆえに、情報更新や管理が比較的容易というメリットがあります。
ストラクチャー型(階層型)
ストラクチャー型は、完成品と部品の関係を階層構造で表す形式です。
「製品Aの下にユニットBがあり、そのさらに下に部品Cがある」といったように、「親子関係」で整理され、部品がどの工程で、どのユニットに使用されるかまで明確にわかります。
この形式は、組立の順序や構成がわかりやすく、設計部門や製造部門で広く活用されているのが特徴です。
特に、設計変更の影響範囲を特定したり、複雑な製品の製造指示を出したりする上で不可欠な情報となります。
BOMの主な種類
製品ライフサイクルの中で、BOMは設計、製造、調達、サービスなど、さまざまな部門で用途や目的に特化して使い分けられています。
部門間の情報共有をスムーズに行うためにも、これらのBOMの種類を正しく把握することが重要です。
設計BOM(E-BOM・設計部品表)
設計BOM(E-BOM:Engineering Bill of Materials)は、製品の設計段階で作成される部品表です。
主にCADデータや図面をもとに、必要な部品構成や数量、技術的な仕様を体系的に整理します。
E-BOMは、設計者が製品の構造を定義する際の基盤となる設計情報であり、「設計情報のマスター」としての役割を果たします。製品がどのように機能するか、どの部品で構成されているかを示し、その後の工程である製造や改良設計にも活用されます。
製造BOM(M-BOM・製造部品表)
製造BOM(M-BOM:Manufacturing Bill of Materials)は、E-BOMをもとに、製造プロセスに適した形に組み替えた部品表です。
設計情報だけでなく、「どこで、どのように作るか」という生産部門の視点が加わります。
具体的には、製造工程の順序や、半製品(中間製品)、加工部品などが追加・修正され、生産計画や生産指示の基礎となります。製造現場での作業効率と品質を左右する重要なBOMです。
購買BOM(P-BOM・購買部品表)
購買BOM(P-BOM:Purchasing Bill of Materials)は、部品の調達・購買業務に特化した部品表です。
E-BOMやM-BOMに含まれる部品の中から、外部から購入する必要がある部品に絞り込み、仕入先の品番や単価、納期、発注ロットなどの購買情報を加えて管理します。
調達部門が効率的に部品を手配し、コスト管理を行うために使用されるのも特徴の一つです。
サービスBOM(Service BOM/S-BOM)
サービスBOM(S-BOM:Service Bill of Materials)は、製品の納入後のメンテナンスや修理、部品交換といったサービス業務に特化した部品表です。
保守部品として必要な品目や、交換手順に関する情報が含まれることが多く、サービス部門や保守部門で活用されます。
製品が市場に出た後に、スムーズなメンテナンスを提供し、顧客満足度を維持・向上させるために重要なBOMです。
現場のBOM管理でよくある課題
多くの企業では、管理方法が原因で業務の足かせになっているのが実情です。
特に、紙やExcelを中心としたアナログな管理体制では、多くの現場が共通の課題を抱えています。
BOMの管理方法によっては業務効率を下げる原因にもなるため、以下のような課題に心当たりがないか、確認してみましょう。
データ・情報の分散
設計部門、生産部門、購買部門など、部門ごとにBOMが別々のファイルで管理されていると、情報が社内に分散してしまいます。
その結果、「どの情報が最新版かわからない」「設計変更の連絡が製造現場の末端まで届いていない」といった状況が発生しがちです。
古い情報にもとづいた手配ミスや、製造現場での作業の手戻りは、リードタイムの遅延につながるおそれがあり、企業全体の生産性を大きく低下させます。
手作業による入力ミス
紙やExcelへの手入力は、人為的なミスを完全になくすのが困難です。
品番の打ち間違いや数量の入力漏れなど、単純なミスが部品不足や仕様違いの製品を生み出す原因となり、品質問題に直結します。
また、図面情報と部品情報が別々に管理されていると、整合性を取るための管理工数も増大するでしょう。
管理工数・運用負荷の増大
仕様変更が発生するたびに、関連する全部署のBOMを手作業で修正し、配布・差し替えを行う作業は大きな負担となります。
特に、製品ライフサイクルが短い製品や、カスタマイズが多い製品を扱う場合、この管理工数が爆発的に増加するでしょう。
また、過去の製品のBOMを探し出すのに時間がかかったり、管理が特定の担当者に属人化したりするケースもあり、増大した運用負荷が、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫してしまいます。
BOM管理を効率化するポイント
これらの課題を解決し、BOMを全社の資産として最大限に活用するためには、BOM管理を効率的に行うための取り組みが不可欠です。
業務プロセスの標準化
BOM管理を効率化するには、関連する業務プロセスの標準化が最も重要です。
品番の採番ルール、部品の登録や更新のフローなどを全社で厳格に定め、部門や担当者によるバラつきをなくします。
この標準化により、すべての部品情報が統一されたルールで管理されるようになり、部門間での認識のズレを防ぎ、精度の高い生産管理の構築に向けた第一歩です。
データの一元管理と共有
BOM管理の非効率性は、「情報共有の不足」と「情報の分散」に原因があります。
この解決には、BOM管理システムや生産管理システム(ERP)などを導入し、設計部門、調達部門、生産部門など各部門が共通のBOMデータベースで一元管理することが必須です。
このシステム化により、BOMの情報更新が全社に即時反映され、連絡漏れや認識のズレを解消できます。
結果として、リアルタイムで正確な情報にもとづいた業務が可能となり、部品管理の効率が飛躍的に向上するでしょう。一元管理は、製造業のDX推進において最大のメリットを生み出す施策です。
周辺システムとの連携
BOMの正確な情報を最大限に活用するためには、周辺システムとの連携も欠かせません。
例えば、CADシステムからBOMを自動作成したり、在庫管理システムや生産スケジューリングシステムと連携させたりすることで、BOMの情報を業務の最前線でダイレクトに活用できます。
これにより、製造現場全体のDXを加速させられるでしょう。現場の実績収集システムなどと連携することで、BOM情報と現場記録が結びつきます。その結果、部品の履歴や製造過程をさかのぼって追跡が可能になります。
BOMを活かした現場DXをi-Reporterで実現
BOM管理システムやERPによる一元管理だけでは不十分です。整備したBOM情報を「いかに現場で活用するか」が、DX推進の鍵となります。
現場帳票ペーパーレス化ソリューション「i-Reporter」は、ERPや生産管理システムなどの外部システムとの連携が可能です。
この機能により、BOM情報をスムーズに取り込み、帳票作成や現場記録に活用できます。
i-Reporterの導入は、現場の工数削減やペーパーレス化に加えて、BOMと実績データの紐づけることにより、トレーサビリティ向上や品質改善にも大きく貢献します。
BOMを起点とした情報共有を徹底し、自社の現場のDXを加速させましょう。BOM管理の効率化を図りたい方におすすめのシステム化ソリューションです。