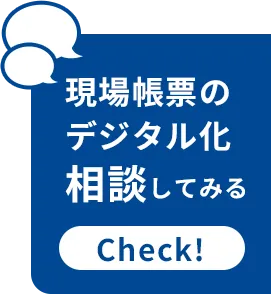目次
「現場のムダをなくしたいが、何から手をつけるべきか」と悩む現場改善担当者は多いのではないでしょうか。
その悩みを解決するのが、業務改善の強力なフレームワーク、「ECRS(イクルス)の原則」です。
本記事では、ECRSの原則の基本から手順、メリット、事例まで徹底解説します。あなたの改善活動が、きっと大きく前に進む手助けになるでしょう。
ECRSの原則(改善の4原則)とは?
ECRSの原則とは、業務プロセスを見直し、改善を進めるためのフレームワーク(思考の枠組み)のことです。
改善の視点を4つのステップに分解し、効果の高い順に検討していくことで、無駄をなくし、効率や生産性の向上を目指します。
ECRSの原則は、以下の4つの視点の頭文字から名付けられています。
• Eliminate(排除):なくせないか?
• Combine(結合):一緒にできないか?
• Rearrange(交換・再配置):順番や場所を変えられないか?
• Simplify(簡素化):もっと楽にできないか?
この原則は、もともと製造業の生産現場で活用されていましたが、その効果の高さから、今では事務作業やサービス業、あらゆる業種・職種の業務プロセスを見直す際の基本中の基本として用いられるようになりました。
ECRSの原則に沿って現場を見つめ直すことで、長年の慣習で見逃されていた非効率な作業を発見できるでしょう。そして、具体的な改善の糸口を見つけることができます。
ECRSの原則を活用する手順
ECRSの原則では、E(排除)→C(結合)→R(再配置)→S(簡素化)の順番での検討が最も重要です。
改善効果が最も高い「排除(E)」から順に取り組むことで、まずは不要な業務を取り除き、無駄な作業を避けながら効率よく改善を進められます。正しい手順で進めることで、少ない労力で大きな成果を得やすくなります。これこそが、ECRSが業務改善のフレームワークとして有効である理由です。
Step1.Eliminate(排除):なくせないか?
改善活動の第一歩は、業務や作業工程の中から「不要なもの」を洗い出し削除することです。
現場の作業やプロセスを一つひとつ確認し、「なぜこの作業を実施しているのか」「この作業の目的は何か」を問い直してください。
もし、実施している理由や目的が曖昧・不明確であったり、すでに他の工程でカバーされていたりする場合は、排除できる可能性が非常に高いです。このステップで業務量を削減することが、最も大きな改善のメリットとなります。
具体例
• 事務作業:誰も内容を確認していない日報や、形骸化した定例会議を廃止する。
• 製造現場:後工程の自動検査でカバーできている、重複した目視検査や記録作業をなくす。
Step2.Combine(結合):一緒にできないか?
排除できないと判断した業務については、次に別々の業務や作業を一つにまとめられないか検討します。
目的や使用するツール、実行するタイミングが似ている作業を統合することで、ムダな「手待ち」や「準備」「移動」といった無駄を排除できます。
特に、担当者間の受け渡しや場所の移動に伴う時間のロスは、結合によって削減しやすい代表的な無駄です。結合によって、情報共有の手間も削減します。
具体例
• 事務作業:複数の担当者がそれぞれ行っていたデータ収集と入力作業を、一人の担当者がまとめて行うことで、データの受け渡しや確認の工数を削減する。
• 製造現場:「ネジ締め」の後に「マーキング」を行っていた工程を、専用の工具を導入するなどして、一つの動作で両方の作業を一度に行うようにする。
Step3.Rearrange(再配置・順序変更):順番や場所を変えられないか?
作業をなくしたり、一つにまとめたりすることが難しい場合は、手順や配置の見直しにより改善を目指します。
作業の順序や、人・モノの動線、設備のレイアウトを最適化し、無理・無駄のないスムーズな流れを作れないか検討しましょう。
作業しやすい環境への再配置は、作業者の負担軽減にも直結します。作業場所の入れ替えも、業務効率を向上させる重要な視点です。
具体例
• 事務作業:承認フローを見直し、上司から担当者への確認といった手戻りの工程をなくし、作業順序を一直線にすることで、待ち時間を削減する。
• 製造現場:部品棚や工具の配置を作業順に沿って置き直し、作業者が探す時間や、無駄な移動距離を短縮する。
Step4.Simplify(簡素化):もっと楽にできないか?
最後に、残った作業を「もっと楽に、簡単にできないか」を考えます。このステップでは、複雑な作業や特定のスキルが必要な業務を、ITツールや治具(作業補助具)を活用して、誰でも・安全に・確実に行えるように改善しましょう。
簡素化は、自動化やシステムの導入といった手段で実現することが多く、デジタル技術の進化により、その可能性は大きく広がっています。このSimplifyの視点は、特に製造業において生産性を向上させる上で重要なポイントです。
具体例
• 事務作業:問い合わせメールへの返信を、定型的なテンプレートを準備し、数クリックで完了できるようにすることで、文章作成の工数を削減する。
• 製造現場:これまで熟練者の勘や経験に頼っていた目視検査を、AIカメラによる画像判定システムに置き換えて、作業の難易度を下げ、品質の安定を図る。
ECRSの原則の活用で得られるメリット
ECRSの原則にもとづいた改善活動は、単に「業務が速くなる」だけではありません。現場の担当者から企業経営に至るまで、幅広いメリットをもたらします。
業務を効率化し、従業員の負担を軽くできる
ECRSの原則は、現場に蔓延する非効率を根本的に解消できるため、従業員の負担を大幅に軽くできます。
特に「排除(E)」や「結合(C)」によって作業の絶対量が減少し、「再配置(R)」によって無理な姿勢や不要な移動が減少します。結果として、従業員の身体的・精神的な負担が軽減され、より安全で働きやすい職場環境が実現しやすくなるでしょう。長期的な人材不足対策としても有効です。
品質を向上させ、属人化の解消につながる
ECRSの原則の「簡素化(S)」は、改善活動において特に品質安定に貢献します。簡素化は、個人のスキルに依存していた複雑な業務を、誰もが遂行可能な標準化されたプロセスへと変更することです。
作業手順が明確になることで、ヒューマンエラーや経験の差による品質のバラつきが抑制され、安定した品質を維持しやすくなるでしょう。さらに、特定の人しかできない「属人化」が解消され、誰もが同じ品質の作業を行える柔軟で強い組織が育ちます。属人化の解消は、組織全体の業務効率と情報共有の質を向上させるでしょう。
コストを削減し、生産性の向上が期待できる
不要な作業やミスの削減は、人件費や材料費といった様々なコストの削減に直結します。例えば、手戻りの作業がなくなればその分人件費を削減でき、ミスの削減は不良品発生による材料の無駄をなくします。
そして、作業が効率化されムダを削減し、企業全体の生産性が向上します。これは、より少ないリソース(時間、労力、コスト)で、より多くの価値を生み出せるようになり、結果として市場での競争力を高めることにつながります。
ECRSの原則を活用する際の注意点
ECRSの原則は強力なフレームワークですが、単なる仕組みの導入だけでは最大限に効果を発揮できません。現場に定着させ、効果を最大化するためには、現場との向き合い方に配慮することが重要です。
現場の協力を得る
改善には現場の協力が不可欠です。トップダウンではなく、現場の意見を積極的に取り入れましょう。現場の知恵は改善のヒントになり、当事者意識が生まれて前向きな活動につながります。改善活動は、現場で働く人々の協力なしには成功しません。
目的やビジョンを共有する
慣れた業務を変える際は、現場は不安を覚えます。「なぜ変えるのか、どんなメリットがあるのか」という目的やビジョンを共有し、対話を通じた合意形成を心がけることで、改善活動は「自分たちの取り組み」になります。
スモールスタートで段階的に進める
大規模な変革は混乱を招きやすいです。まずは特定の部署や影響範囲の小さい業務からスモールスタートで試し、小さな成功体験を積み重ねましょう。そのノウハウを共有し、徐々に他の部署へ展開していく段階的なアプローチが、確実な定着につながります。
ECRSの原則を活用した改善事例
ECRSの原則は、特にITツールの導入と組み合わせることで、大きな効果を発揮します。
ここでは、ある製造現場で、帳票の電子化システムを導入し、簡素化(Simplify)を推進した改善事例をご紹介します。
【改善前】
• 数百か所に及ぶ部品の測定結果を、手書きで紙の帳票に記録していた。
• 記録後、事務所に戻ってからExcelに手作業で転記し、日報やグラフを作成していた。
• 報告会のために、別途KPIの進捗をまとめた資料を作成する必要があった。
【改善後のECRSの適用】
• 簡素化(S):タブレットを用いて、現場で測定結果を直接システムに入力。手書きの手間を大幅に削減できます。
• 排除(E):紙の帳票からExcelへの手書き・転記作業を完全に排除。また、システムが自動で日報やグラフを作成するため、報告資料の作成が不要になった。
• 再配置(R):故障要因や対策の進捗がリアルタイムで可視化され、事務所に戻らず現場で状況確認できるようになった。
この改善により、作業者はこれまで転記作業や資料作成に費やしていた時間をなくし、本来のコア業務である品質改善や設備保全の分析に、より多くの時間を充てられるようになりました。結果として、現場全体の改善サイクルが加速しています。
ECRSの原則で現場のムダをなくし、デジタルトランスフォーメーションを加速
ECRSの4つの視点(排除・結合・再配置・簡素化)で現場を一つひとつ見直すことで、具体的な改善の糸口を発見できるでしょう。
特に、最後のステップである簡素化(S)は、ITツールの活用によって効果を高めることができます。
現場のムダをなくし、より付加価値の高い仕事に集中するための手段として、現場帳票システム「i-Reporter」は強力な選択肢となります。
現場帳票システム「i-Reporter」を導入する効果
現場帳票システム「i-Reporter」の導入は、ECRSの原則、特に簡素化(Simplify) を強力に推進し、以下のような効果をもたらします。
• 報告業務の簡素化と負担軽減
• コア業務への集中
• PDCAサイクルの加速
報告業務の簡素化と負担軽減により、現場での手書きやExcelへの転記といった無駄な作業をなくし、記録作業の負担を軽減できます。
これにより、従業員は付加価値の高いコア業務(分析や改善策の検討など)に集中できるでしょう。さらに、データをリアルタイムで収集・共有できるため、意思決定のスピードが向上し、現場改善のPDCAサイクルが加速します。
ECRSの原則にもとづいた体系的な改善活動と、現場DX(デジタルトランスフォーメーション)を強力に推進する現場帳票システム「i-Reporter」の導入を組み合わせることで、あなたの現場DXを大きく加速させることが可能になります。