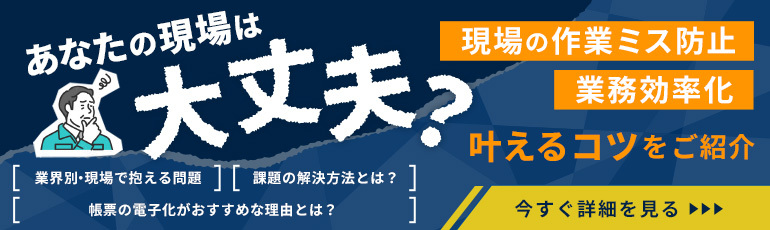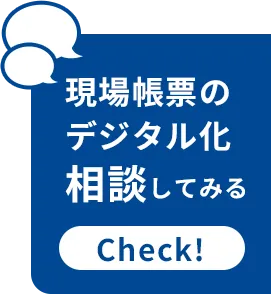目次
製造業やサービス業において、製品やサービスの品質を維持・向上させることは、顧客満足度を高め、企業の信頼性を確立する上で重要です。
その中心となるのが「品質管理(QC)」と「品質保証(QA)」という二つの大切な概念です。
この記事では、品質管理(QC)の基本的な定義から、品質保証(QA)との違い、具体的な手法、そして実施する上でのメリットや注意点について詳しく解説します。
品質管理と品質保証への理解を深め、日々の業務改善に役立てていただければ幸いです。
QC(品質管理)とは?
QC(品質管理)とは、「Quality Control」の略語です。製品やサービスの品質基準を一定に保つための活動、手法を指します。
具体的には、原材料の検査や製造工程の管理・改善などがQC活動に含まれ、製品やサービスの品質を一定の基準に保つための活動全般です。
たとえば、製造工程やサービス提供の各段階において、品質目標を設定し、それを達成するために必要な検査、測定、分析、改善などの活動を行い、不良品の発生を未然に防ぎ、顧客に高品質な製品やサービスを提供することが目的です。
日本では、職場内で結成された小グループが主体的に品質管理に取り組むQCサークル活動が伝統的に行われてきました。
しかし、昨今は人手不足や働き方改革などによる省人化のニーズから、DXツールで品質管理を支援・合理化する動きも見られるようになっています。
QA(品質保証)とは?
QA(品質保証)とは、製品やサービスが規定の品質基準を満たしていることを保証するための全体的な活動を指します。
品質保証の目的は、製品やサービスの品質を確保し、顧客の安心と満足を保証することです。
その対象範囲は、製品やサービスの企画・開発段階から、製造、販売、そして販売後のアフターフォローまでと広範囲に及びます。
QA(品質保証)の主な業務内容
品質保証の主な業務内容は多岐にわたり、製品の仕様書や規格書の作成、原材料や製造工程の品質調査、完成品の品質検査などが挙げられます。
また、顧客からのクレーム対応とその原因調査、市場調査や顧客ニーズの分析なども重要な業務です。
これらの活動を通じて、顧客が求める品質を確実に提供するための仕組みづくりと運用を行います。
QC(品質管理)とQA(品質保証)の違いとは
品質管理(QC)と品質保証(QA)は、どちらも製品やサービスの品質に関わる重要な活動ですが、その目的、責任範囲、時間軸、業務範囲には明確な違いがあります。
QC(品質管理)とQA(品質保証)の違い
品質管理(QC)は、主に製造工程内における不良品の発生防止に焦点を当てた活動です。
一方、品質保証(QA)は、製品企画から販売後の顧客対応まで、より広範な範囲で顧客満足度と信頼性の向上を目指します。
QCが製品完成までの品質維持をカバーする一方で、QAは製品完成後も含めた全体的な品質をカバーするのが特徴です。
業務範囲においても、QCは製造工程に限定されることが多いのに対し、QAは企画、設計、製造、販売後の対応までと広範囲に及びます。
具体的な業務内容の例としては、QCが完成品の目視検査や寸法測定、機能テストなどを実施するのに対し、QAは品質マニュアルの作成や教育・訓練体制の構築などを行いましょう。
| QC(品質管理) | QA(品質保証) | |
| 目的 | 不良品の発生防止 | 顧客満足度と信頼性の向上 |
| 責任範囲 | 製造工程内での不良品防止 | 製品企画から販売後まで全体的な責任 |
| 時間軸 | 製品完成まで | 製品完成後も含む |
| 業務範囲 | 製造工程のみ | 企画、設計、製造、販売後対応まで(広範囲) |
| 業務内容の例 | 完成品の目視検査、寸法測定、機能テストなど | 品質マニュアルの作成、教育・訓練体制の構築など |
QC(品質管理)とQA(品質保証)の関係性
QC(品質管理)とQA(品質保証)は、自社製品の品質向上と顧客満足度の向上という共通の目的を持つ、相互補完的な関係です。
品質管理(QC)は、品質保証(QA)が構築する品質保証体制の枠組みの一部として機能しており、製造工程における具体的な品質管理活動を通じて、製品の品質を確保します。
両者を効果的に連携させることで、より高品質な製品やサービスの提供が可能となり、顧客からの信頼を得ることにつながるでしょう。
QCの7つの道具
品質管理(QC)活動において、問題解決や品質改善のために古くから活用されてきた基本的な手法が「QCの7つ道具」です。
これらの道具は、データの収集・整理・分析を視覚的に行い、品質に関する問題を効率的に把握し、対策を立てる上で非常に有効になります。
QCの7つの道具とは?
QC7つ道具とは、品質管理のためにデータを整理・分析するための手法です。問題点の見える化や原因追及に役立ちます。
パレート図
問題や不良の要因を頻度順に棒グラフで示し、累積比率を折れ線グラフで可視化する手法です。
どの項目が全体に対して大きな影響力を持っているかを一目で把握できるため、対策を講じるべき重要な問題に優先順位をつけることができます。
エクセルなどで作成する際は、データを降順に並べ替え、各項目の累積比率を算出して複合グラフを作成するのが一般的な手順です。
特性要因図(フィッシュボーン図)
問題の根本原因を明確にするために、結果(特性)とそれに影響を与えると考えられる要因を、魚の骨のような形状の図で体系的に整理する手法です。
原因は「6M(人:Man、機械:Machine、材料:Material、方法:Method、測定:Measurement、環境:Milieu/Mother Nature)」などのカテゴリに分類され、さらに各要因を細かく分析することで、問題の真の原因を特定しやすくなります。
グラフ
データを視覚的に表現することで、数値だけでは分かりにくい傾向やパターンを把握するのに役立ちます。
棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフなど、データの種類や目的に応じて適切なグラフを選択することが重要です。
例えば、経時的な変化を見るには折れ線グラフ、構成比率を見るには円グラフが適しています。
ヒストグラム
集団内のデータの分布状態を把握するために使用されるグラフです。
データをいくつかの階級に分け、各階級に属するデータの度数を棒で示します。
これにより、データの中心傾向、ばらつき、分布の形状などを視覚的に捉えることができ、品質の安定性や異常の発見に役立つでしょう。
散布図
2つの異なるデータの間にどのような関係があるか(相関関係)を分析するためのグラフです。
一方のデータを横軸、もう一方のデータを縦軸に取り、データを点としてプロットします。
点の分布を見ることで、正の相関(一方が増えると他方も増える)、負の相関(一方が増えると他方は減る)、または相関がないといった関係性を把握することができます。
管理図
工程が安定した状態にあるかどうかを時系列的に監視するためのグラフです。
品質特性の測定値を一定期間にわたってプロットし、管理限界線(上限管理限界、中心線、下限管理限界)を設けることで、異常な変動や傾向を早期に発見し、対策を講じることができます。
チェックシート
あらかじめ決められた項目について、実施状況や不良の発生状況などを簡単に記録・集計するためのツールです。
点検漏れを防いだり、不良の種類や発生場所などを効率的に把握したりするのに役立ち、収集したデータは、パレート図やヒストグラムなどの分析に活用されます。
新QCの7つの道具
複雑化する現代の品質管理に対応するために、従来のQCの7つ道具を補完する形で生まれたのが「新QCの7つ道具」です。
これらは、言語データや非数値データを扱うのに適しており、問題の構造化や原因の特定、対策の立案などに活用されます。
親和図法
収集した多くの言語情報(アイデア、意見、問題点など)から、類似性のあるものをグループ化し、それらの関連性を明確にする手法です。
複雑な問題を整理し、本質的な課題や新たな視点を見つけ出すのに役立ちます。
連関図法
問題に関わる複数の要因間の複雑な因果関係を、矢印を用いて図で表現する手法です。
どの要因が他の要因に影響を与えているのか、根本原因は何かなどを視覚的に把握し、問題解決のための糸口を見つけ出すのに活用されます。
系統図法
目的を達成するための手段や対策を、階層的に展開していく手法です。
「目的」から始まり、「一次手段」「二次手段」…と、具体的な行動レベルまで細分化していくことで、効果的な対策を漏れなく検討することができます。
マトリックス図法
問題に関わる複数の要素間の関係性を、行と列で構成された表(マトリックス)で分析する手法です。
各要素の交点に記号や数値を用いて関連性の強さを示すことで、重要な要素や着眼点を見つけ出すことができます。
アローダイアグラム法
プロジェクトの工程管理に用いられる手法で、作業の順序や所要時間を視覚的に表現します。
クリティカルパス(最も時間がかかる経路)を特定することで、プロジェクト全体の納期管理や効率化を図ることができるでしょう。
PDPC法(Process Decision Program Chart)
予測される事態の展開に応じて、事前に複数の対策案を検討しておくための手法です。
予期せぬ問題が発生した場合でも、あらかじめ準備しておいた対策を実行することで、混乱を最小限に抑え、リスク対応を事前に準備できます。
マトリックスデータ解析法
多変量データから、要素間の関係性をより客観的に数値で分析する手法です。
複雑なデータ構造を分かりやすく可視化し、潜在的な要因や構造的な問題を発見するのに役立ちます。
QCの代表的な手法
QC(品質管理)活動は、QCの7つ道具や新QCの7つ道具以外にも、様々な手法を用いて行われます。
ここからは、代表的な手法として、職場の環境整備から統計的な分析、問題解決のためのストーリーまで、幅広いアプローチをみていきましょう。
5S
5Sは、職場の環境を整理・整頓・清掃・清潔にし、それらを維持するための習慣(しつけ)を指す、品質管理の基本的な手法の一つです。
以下の5Sを徹底することで、無駄を排除し、効率的で安全な作業環境を実現することができます。
- 整理
必要なものと不要なものを分け、不要なものを職場から排除します。 - 整頓
必要なものがすぐに取り出せるように、置き場所や置き方を決め、表示を明確にします。 - 清掃
職場全体を清掃し、ゴミや汚れのない状態を保ちます。 - 清潔
整理・整頓・清掃の状態を維持するために、ルールや手順を定め、定期的に点検します。 - しつけ
定められたルールや手順を守る習慣を身につけ、全員で5Sを継続的に実践します。
職場環境の向上には、まず必要なものと不要なものを分け、不要なものを排除する整理が重要です。
次に、必要なものをすぐに取り出せるよう置き場所を決め表示する整頓、そしてゴミや汚れのない状態を保つ清掃が不可欠で、これらの状態を維持するためにルールを定め定期的に点検する清潔、そしてルールを守る習慣を身につけ継続的に実践するしつけが重要となります。
これら5Sの実践が、より快適で効率的な職場へと繋がります。
IE (Industrial Engineering)
IE(Industrial Engineering)は、人と設備、資源の効率的な活用を目指し、作業方法や生産システムを最適化する手法です。
時間研究、動作研究、レイアウト設計、設備配置などの手法を用いて、作業時間の短縮、コスト削減、品質向上などを図ります。
4M
4Mとは、品質に影響を与える4つの要素「Man(人)、Machine(機械)、Material(材料)、Method(方法)」の頭文字を取ったものです。
品質問題を分析する際に、これらの要素のいずれか、または複数の組み合わせが原因となっていないかを検討します。
TQC (Total Quality Control)
TQC(全社的品質管理)は、組織全体のあらゆる部門が品質管理に参画し、顧客満足度の向上を目指す活動になります。
トップマネジメントのコミットメントの下、全員参加で品質改善に取り組むのが特徴です。
TQM (Total Quality Management)
TQM(総合的品質管理)は、TQCの考え方をさらに発展させたもので、品質だけでなく、コスト、納期、サービスなど、企業のあらゆる側面における品質向上を目指す経営管理手法です。
顧客重視の考え方を基本とし、継続的な改善活動を通じて組織全体のパフォーマンスを高めます。
SQC(統計的品質管理)
SQC(Statistical Quality Control)は、統計的な手法を用いて品質を管理するアプローチです。
データのばらつきを考慮しながら、以下のように科学的な根拠に基づいて品質を評価し、管理・改善を行います。
- 検定と推定
サンプルデータから母集団の特性を推定し、品質基準との適合性を統計的に判断します。 - 相関分析
2つの変量間の関係性の強さや方向性を分析し、品質特性に影響を与える要因を特定します。 - 回帰分析
2つの変数間の関係を数式でモデル化し、一方の変数の値から他方の変数の値を予測します。 - 実験計画法
効率的にデータを収集し、品質に影響を与える要因とその影響度を科学的に評価するための実験計画を立てます。 - 多変量解析法
複数の品質特性や要因間の複雑な関係性を分析し、品質改善のための重要な知見を得ます。 - 直交多項式
実験データなどの近似に用いられ、データの傾向を把握したり、予測モデルを構築したりするのに役立ちます。 - 二項確率紙
不良品の発生確率など、二項分布に従うデータの管理に用いられる特殊なグラフ用紙です。 - 簡易分析法
現場で手軽に実施できる基本的な統計的手法で、品質データの日常的な管理や問題の早期発見に役立ちます。
品質管理における統計的手法は多岐にわたり、検定と推定は、サンプルデータから母集団の特性を推測し、品質基準との適合性を統計的に判断する基礎となります。
相関分析は二つの変量間の関係性を明らかにし、品質特性に影響する要因を特定し、回帰分析はその関係を数式化し、予測に活用できるのが特徴です。
効率的なデータ収集と要因評価には実験計画法が有効であり、複数の要因が絡む複雑な関係性の分析には多変量解析法が用いられます。
データの近似や傾向把握には直交多項式が、不良品の管理には二項確率紙が役立ち、日常的な品質管理や問題の早期発見には、現場で手軽に使える簡易分析法が重要です。
QCストーリー
QCストーリーは、品質管理活動を効果的に進めるための、問題解決の手順を示したものです。以下のステップに従って、組織的に品質改善に取り組みます。
- テーマの選定
取り組むべき問題や改善課題を明確に定義します。 - 現状把握
選定したテーマに関する現状のデータを収集・分析し、問題の大きさを把握します。 - 目標設定
現状分析の結果に基づき、具体的な改善目標を設定します。 - 活動計画
目標達成のために、いつ、誰が、何を、どのように行うかを計画します。 - 原因解析
問題の真の原因を特定するために、特性要因図などを活用して分析を行います。 - 対策立案
特定された原因に対する具体的な対策案を検討し、実行計画を立てます。 - 対策実施
立案した対策を実行に移します。 - 効果確認
実施した対策の効果をデータに基づいて検証します。 - 標準化と管理
効果が認められた対策を標準化し、再発防止のための管理体制を構築します。 - 反省と今後の方針
QCストーリー全体の活動を振り返り、得られた教訓や今後の改善の方向性を検討します。
品質改善活動は、まずテーマ選定で取り組む課題を明確化し、現状把握でデータに基づき問題の大きさを把握しましょう。
次に具体的な目標設定を行い、達成に向けた活動計画を策定します。原因解析で真因を特定し、対策立案・実施へと進みます。
対策の効果確認をデータで行い、効果があれば標準化と管理体制を構築し、活動全体を振り返り、教訓や今後の方向性を定める反省と今後の方針へと繋げましょう。
この一連の流れが品質改善のQCストーリーです。
QC(品質管理)やQA(品質保証)を実施するメリット
品質管理(QC)や品質保証(QA)を適切に実施することは、単に製品やサービスの品質を高めるだけでなく、企業の経営全体に多くのメリットをもたらします。
業務プロセスの標準化による効率化
品質管理や品質保証の手法を導入することで、業務プロセスが明確化され、標準化が進みます。
作業の手順や基準が統一されるため、従業員は同じ認識で業務に取り組むことができ、作業の無駄やバラつきが減少するでしょう。これにより、業務効率が向上し、生産性の向上にもつながります。
クレームとトラブルの未然防止
品質管理と品質保証の活動は、製品やサービスにおける欠陥や不具合の早期発見と改善を可能にします。
その結果、顧客からのクレームやトラブルを未然に防ぎ、顧客満足度の向上に大きく貢献するでしょう。
顧客からの信頼獲得は、持続的なビジネス成長の基盤となるため、これらの活動は極めて重要です。
不良品の削減によるコスト削減
品質管理を徹底することで、製造工程における不良品の発生を抑制できます。
これは、無駄な材料費や再作業コストの削減につながり、資源の有効活用につながるでしょう。
さらに、不良品が市場に出回るリスクを低減することで、返品や修理対応にかかるコストも削減でき、経済的なメリットをもたらします。
信頼性向上によるブランド価値の強化
高品質な製品やサービスを提供し続けることは、顧客からの信頼を高め、企業のブランド価値を向上させます。
品質管理や品質保証がしっかりと実施されている企業は、顧客にとって安心して製品やサービスを利用できる対象です。
高い信頼性は、リピーターの増加や新規顧客の獲得につながり、競争優位性を確立する上で重要な要素となります。
QC(品質管理)やQA(品質保証)を実施する際の注意点
品質管理(QC)や品質保証(QA)は多くのメリットをもたらしますが、実施する際にはいくつかの注意点があります。
これらの点に注意することで、より効果的な品質管理・保証体制を構築し、その効果を最大限に引き出すことができるでしょう。
品質と効率のバランスを考える
品質を高めるために過度な検査や管理を行うと、作業時間やコストが増加し、生産効率が低下する可能性があります。
品質と効率のバランスを考慮し、最適な管理レベルを設定することが重要です。
形式的な運用にしない
チェックリストやマニュアルを作成しても、それが形骸化し、形式的な運用になってしまうと、本来の目的である品質向上には繋がりません。
運用する際には、「なぜそれを行うのか」という目的意識を従業員全体で共有し、意味のある活動にすることが重要です。
部門間で情報を共有する
品質管理や品質保証は、特定の部門だけでなく、企画、開発、製造、販売など、関連する全ての部門が連携して取り組む必要があります。
部門間で情報を共有せずに独立して活動してしまうと、全体としての品質管理がバラバラになり、効果が半減する可能性もあるでしょう。
定期的なコミュニケーションを通じて、品質に関する情報を共有し、連携を強化することが大切です。
運用ルールを定期的に見直す
生産環境や市場ニーズは常に変化するため、品質管理や品質保証の運用ルールもそれに合わせて見直す必要があります。
定期的なレビューを行い、必要に応じて改善を加えることで、常に最適な管理体制を維持することができるでしょう。
品質管理と品質保証の効率化にはDXツールの活用を!
品質管理(QC)と品質保証(QA)の効率化には、DXツールの活用が不可欠です。
特に製造業において重要なQC活動は、顧客満足度と競争力向上に貢献しますが、人手不足の現状では十分な時間と労力を割けない場合があります。ヒューマンエラーのリスクを減らし、省人化・合理化を図るためには、QCへのDXツール導入が有効です。
そこで、おすすめしたいDXツールが現場帳票電子化システム「i-Reporter」です。
iPhoneやiPad、Windowsといった手持ちの端末で、製造現場の入出庫・棚卸・ピッキング業務を大幅に効率化できるでしょう。この機会にぜひご検討ください。