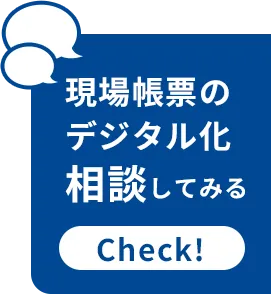ハンディターミナルとは?主な機能や仕組み、導入するメリットを解説
目次
商品管理や在庫の精度向上、作業の効率化を求める現場で広く活用されているのが、ハンディターミナルです。物流業界や製造業界、小売業界をはじめとしたさまざまな分野で、データの入力・収集を迅速かつ正確に行える点が評価されています。
とくに、近年では、OCRや自動処理のアプリケーションと連携するケースも増えており、OSや操作性、バッテリーの持続時間を含めた選定が重要視されるようになりました。本記事では、ハンディターミナルの仕組みや機能から、活用事例や導入のメリット・デメリットまで、幅広く解説します。
ハンディターミナルとは
ハンディターミナルとは、手に持って操作する携帯型の業務端末で、バーコードや2次元コードを読み取ったり、データの入力・送信を行ったりするために使用されます。バーコードリーダーや2次元コードリーダーのほか、スキャナや液晶ディスプレイ、キーボードも搭載されており、現場のさまざまな作業に対応可能です。
主に、在庫管理や棚卸し、入出庫作業やピッキングなどで利用されており、物流業界や製造業界では長年にわたり導入されてきました。近年は、小売業でもアプリケーションとの連携を通じて活用の幅が広がっています。
ハンディターミナルの仕組み
ハンディターミナルは、まずスキャナ部でバーコードや2次元コードを読み取るところから動作が始まります。取得した情報を本体内で処理・保存し、必要に応じてUSBやクレードル、有線・無線LANやBluetoothなどを介して、パソコンやサーバーにデータを送信する仕組みです。
なかでも、無線LANやBluetoothのアンテナを搭載したモデルであれば、リアルタイムでの情報共有にも対応可能です。現場と本部の間でデータを即時に反映でき、情報の一元化や業務のスピードアップに貢献します。
ハンディターミナルの主な機能
ハンディターミナルは、現場作業の効率化に役立つ機能を多く備えた業務用端末です。以下に代表的な機能を挙げます。
・データの収集・記録:バーコードや2次元コードを読み取ってデータを収集し、記録
・データの送受信:収集したデータをPCやサーバーに送受信
・画面表示:読み取ったデータや指示などを画面に表示
・キー入力:キーボードでデータを入力
・音声入力:音声でデータを入力できる機能も搭載されている機種もある
これらの機能により、単なるバーコードの読み取りだけでなく、入力・確認・送信などの業務処理まで、一台で完結できます。なかには、音声入力に対応したモデルもあり、現場の作業環境に応じた柔軟な運用が可能です。
従来の手作業に比べて作業スピードが向上するほか、入力ミスや見間違いといったヒューマンエラーの防止にもつながります。
ハンディターミナルとバーコードリーダーの違い
ハンディターミナルとよく似た機器の一つが、バーコードリーダーです。両者はどちらもバーコードの読み取りに使われますが、機能には明確な違いがあります。
バーコードリーダーは、主にデータの読み取りに特化した機器で、読み取った情報は他の端末で処理する必要があります。一方、ハンディターミナルは読み取りだけでなく、その場でデータの確認・編集・送信まで完結できる点が大きな特徴です。
情報の即時処理と表示が可能な点が、大きな違いといえるでしょう。
ハンディターミナルの主な活用シーン
ハンディターミナルは、さまざまな業界で現場業務の効率化に役立てられています。ここでは、物流・製造・小売・医療など、現場での具体的な活用例を見ていきましょう。
倉庫内でのピッキング作業
ハンディターミナルには、出荷指示や保管場所などの情報を表示できる機能があります。倉庫内のピッキング作業で使えば、表示された情報を確認しながら商品を取り出し、バーコードを読み取って品番の正誤判断に役立つはずです。
ハンディターミナルによって誤出荷を防げるため、出荷精度の安定にもつながるでしょう。
製造業での棚卸し
商品に貼られたバーコードをハンディターミナルで読み取ることで、棚卸データや出庫記録の即時登録が可能です。製品や部品の在庫の追跡や履歴管理が可能になり、過不足や紛失の早期発見につながります。
小売業での在庫管理
店舗内での在庫確認や発注作業にも、ハンディターミナルは役立ちます。店舗に設置された端末で商品のバーコードをスキャンするだけで、在庫数や販売状況を即座に把握できるため、在庫確認や発注業務を迅速に行えるでしょう。
病院での医療情報管理
医療現場では、ハンディターミナルが患者情報の把握や管理に幅広く導入されています。バーコード付きのリストバンドやカルテを読み取り、診療履歴や検査結果、投薬内容などをその場で確認することが可能です。
バーコードを利用した患者の医療情報の管理は、投薬ミスをはじめとする医療過誤の予防に役立ちます。
ハンディターミナルのメリット
ハンディターミナルは、現場業務の効率化や情報の精度向上に大きく貢献する端末です。ここでは、導入によって得られる主なメリットをご紹介します。
業務効率化と生産性が向上する
手作業で行っていた業務をハンディターミナルでデジタル化すれば、入力や確認の手間を省け、作業時間の大幅な短縮が可能です。とくに、目視での商品名や品番の確認作業が不要になることで、入出荷検品やピッキング、棚卸しといった現場作業のスピードが上がるでしょう。
作業の効率化により、スタッフの負担も軽減されるため、生産性の向上も期待できます。
ヒューマンエラーを防止しデータ精度が向上する
手書きや目視での作業では、転記ミスや記入漏れといったヒューマンエラーが起きやすく、商品数の数え忘れや入力ミスの原因となっていました。ハンディターミナルを使用し、商品マスタと照合すれば、品番や数量の間違いをその場で検知でき、ミスを未然に防ぐことが可能です
棚卸し時の在庫差異も少なくなるため、在庫データ全体の精度が高まります。
リアルタイムな情報共有で管理を高度化できる
無線タイプのハンディターミナルを使えば、現場での操作内容が即座にシステムに反映され、常に最新の情報に基づいた業務判断が可能です。正確なデータがリアルタイムで手に入ることで、欠品や過剰在庫のリスクを低減できます。
発注や生産計画に関する意思決定がスムーズに行えるようになるため、在庫の最適化や納期の安定につながるでしょう。
ハンディターミナルのデメリット
ハンディターミナルは多くの現場で活用されている一方で、導入や運用にあたって注意すべき点もいくつか存在します。ここでは、代表的なデメリットを整理しておきましょう。
導入コストがかかる
ハンディターミナルを導入する際は、本体の購入費に加え、運用や保守に関する費用も必要です。さらに、ハンディターミナルの法定耐用年数は5年とされており、機器の老朽化に応じた定期的な入れ替えも求められます。
なお、実際の使用年数は機種や利用環境によって異なり、早期に故障するケースもあり、どの程度の費用がかかるかを、あらかじめ把握しておくことが大切です。
バーコードの準備や読み取りに手間がかかる
バーコードを活用するには、事前の準備が欠かせません。在庫や棚に対応するバーコードを事前に用意し、それぞれに貼り付けておく作業が発生します。
例えば、在庫管理や棚卸しでは、商品ごとにバーコードをスキャンする必要があり、作業の手間が増えるケースも少なくありません。とくに、取り扱う品目数が多い現場では、バーコードの準備と読み取りが作業者の負担となることもあるでしょう。
スキャン漏れ・通信エラーのおそれがある
バーコードの印字不良やラベルの劣化が進行すると、情報を正確に判別できず、読み取りエラーが発生しやすくなります。また、端末のスキャナ感度が低下している場合、スキャン漏れが起きる可能性も否定できません。
このような読み取りミスは、在庫数の誤差や検品ミスといった、さまざまな業務上のトラブルに直結します。さらに、無線接続時には、通信エラーによりデータが正しく送信されず、情報が反映されないといったリスクも伴うため注意が必要です。
ハンディターミナルとは異なる仕組みで現場を変える「i-Reporter」
ハンディターミナルは、宅配業者などの物流業界、製造業界や小売業界の現場で使用されている便利なツールですが、導入や運用にかかるコストの高さや、用途が限定されやすいという課題も抱えていました。こうした制約を踏まえ、スマートフォンやタブレットを業務用端末として活用する動きが広がりつつあります。
株式会社シムトップスが提供する「i-Reporter」は、既存の携帯端末やスマートデバイスを活用し、帳票業務をデジタル化するツールです。ハンディターミナル専用機に比べ、導入コストを5分の1以下に抑えられるケースもあり、初期費用を抑えながら業務改善を進めたい企業に適しています。
また、単なる帳票入力にとどまらず、ペーパーレス化やデータのリアルタイム反映、蓄積情報の活用による現場改善など、広範囲で大幅な効果が期待できます。製造業や物流業をはじめ、さまざまな業種で導入が進んでいる点からも、実用性の高さがうかがえるでしょう。
ハンディターミナルの代替を検討している現場では、「i-Reporter」の柔軟性と拡張性が、より実用的な運用につながりますので、ぜひ導入をご検討ください。