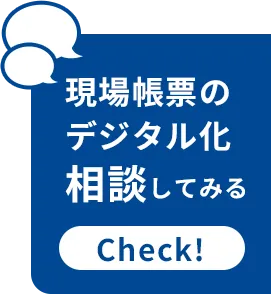リスクアセスメントの書き方とは?実施時期や手順、製造業の記載例
目次
毎日の業務を滞りなく進めるために、現場に潜む「危険」を見える化し、先回りした対策は不可欠で、危険の特定手法が「リスクアセスメント」です。
「リスクアセスメントを導入したいが、具体的に何から始めればいいのかわからない」「正しい書き方が知りたい」とお考えの現場の担当者や、管理者の方も多いでしょう。
本記事では、リスクアセスメントの基本から、実施が義務となる時期、正しい書き方や手順、そして製造業での記載例まで、詳しく解説します。
リスクアセスメントの基礎知識
リスクアセスメントは、労働災害を未然に防ぐための、体系的な安全管理手法です。本トピックでは、その定義や目的、実施が必要なタイミングといった基礎を確認しましょう。
リスクアセスメントとは
リスクアセスメントとは、職場や業務上の潜在的な危険性や有害性を事前に調査する手法です。まず、リスクの大きさ(発生する可能性と被害の程度)を評価します。そして、必要な対策を検討・実施する一連のプロセスを指します。
リスクアセスメントの目的
リスクアセスメントは、労働災害や健康障害の発生を未然に防ぐのが主な目的です。
潜在的な危険性や有害性を把握し、先回りして対策を講じることで、従業員を守り、安心して働ける職場を作ることができます。
また、リスクの大きさに応じて対策の優先順位を決定すれば、限られた資源の中で効率的に安全を確保できるでしょう。
リスクアセスメントの法律上の位置づけ
労働安全衛生法第28条の2により、リスクアセスメントの実施は事業者の努力義務となっています。
製造業を含め、建設業、卸売業、小売業など、幅広い業種が対象です。特に、一定の危険有害性のある化学物質を製造・取り扱う事業場では、リスクアセスメントの実施が法律で義務付けられています。
【出典】 「職場のあんぜんサイト」 (厚生労働省) 「労働災害を防止するため リスクアセスメントを実施しましょう」 (厚生労働省)
リスクアセスメントの実施時期
リスクアセスメントは、一度行えば終わりではありません。
職場の状況に変化があった際には、必ず見直しを行う必要があります。労働災害の発生を未然に防ぐため、リスクアセスメントの実施時期の例として、次のような場合が挙げられます。
• 新規に対象物(機械設備や化学物質など)を採用・変更するとき
• 作業手順や作業方法を新たに採用・変更するとき
• 設備や建設物の設置・移転・変更・解体時
• 労働災害が発生したとき(過去のリスク評価の見直し)
• 新しい危険や有害性の情報が提供されたとき(例:SDSの更新など)
• 機械設備の経年劣化やリスク状況の変化が認められたとき
• 設計段階の各段階(構想設計、詳細設計、試作機など)
新規設計の機械の場合は、設計の初期段階から複数回に分けてリスクアセスメントを行うと良いとされています。
会社として実施するタイミングのルール化も推奨されています。これにより、安全リスクを早期に把握し、対策を講じることができるでしょう。
リスクアセスメントの実施手順
リスクアセスメントは、以下の3つの手順で構成されます。この手順に従って体系的に進めることが、網羅的なリスクの洗い出しにつながるでしょう。
Step1.危険性や有害性の特定
職場にどのようなリスクの原因(リスク源)が存在するかを洗い出す作業です。
作業環境や機械、設備、原材料、作業行動、周囲の環境などから従業員の死亡、ケガ、健康障害を引き起こす可能性のある危険要素を特定します。
危険性や有害性の特定段階では、現場の作業者の意見も聞き、過去のヒヤリハットや事例も参考にして網羅的に抽出することが大切です。
Step2. リスクの見積もりと優先度の決定
特定した危険性や有害性に関して、「事故が発生する可能性(可能性の度合い)」と「発生した場合の被害の程度(被害の度合い)」を見積もりましょう。
この2つの要素を組み合わせて、各リスクの大きさを算出します。算出した結果に基づき、対策を講じる優先順位を決定します。特にリスクの大きいものから優先的に対策を行うのがポイントです。
Step3. リスク低減措置の検討・実施
優先順位が決定したら、リスクを低減させるための具体的な措置を検討し、実施します。
低減措置は、「本質的な対策(危険な作業や物質の排除、変更)」「工学的な対策(安全装置の設置)」「管理的な対策(作業手順の明確化、立ち入り禁止など)」「個人保護具の使用」の順序で検討するのが原則です。
安全対策を実施した後は、必ずリスクがどこまで低減されたかを再評価し、記録することが求められます。
リスクアセスメントの基本的な書き方
リスクアセスメントの記録には、リスクアセスメントシートの使用が多いため、書き方を統一することが重要です。
特に厚生労働省の「リスクアセスメント記録表」を参考にすると、実務で使いやすい形で記録を残せます。その結果を踏まえて、継続的な改善につなげましょう。
リスクアセスメントの記載項目
リスクアセスメントシートに記載すべき主な項目は以下の通りです。
• 基本項目
対象事業場、実施年月日、施設管理者・実施者などを記載します。誰が、いつ、どこで実施したかを明確にするために不可欠な情報です。
• 作業名・工具・機械設備名
作業名は、業務の内容がわかるように具体的に記載します。(例:「倉庫内での区画整理作業」や「工場ラインにおける部品組み立て」など)工具や機械、設備が対象の場合は、特定がしやすいように設置場所も併せて記入しましょう。(例:「輸送用コンベア(1号機・組立ライン3階)」や「電動ドリル式ねじ締め機」など)
• 危険性・有害性により発生のおそれのある災害
特定した危険要素から具体的にどのような災害が発生するおそれがあるかを記載します。例:「コンベアに巻き込まれて手を挟む」「化学物質の蒸気を吸い込んで健康障害を起こす」など、原因と結果を明確につなげて記述します。
• 既存の災害防止対策
現時点で実施されている対策を記載しましょう。(例:「安全カバーの設置」「作業手順書の掲示」「防塵マスクの着用」など)既存の対策の有無が、次のリスクの見積もりに影響します。
• リスクの見積り
発生可能性と被害の程度を組み合わせ、数値やランクでリスクの大きさを算出した結果を記入します。リスク評価は定量化すると対策の優先順位がつけやすいでしょう。
• リスク軽減策
見積もられたリスクを許容できるレベルまで低減させるための新たな措置を具体的に記載します。(例:「センサー式停止装置の導入」「作業前点検チェックリストの導入」など)
• リスク低減対策実施後のリスク評価
リスク軽減策を実施した後、再度リスクを見積もった結果を記載します。対策が十分に機能し、リスクが許容できる範囲に収まったかを確認するために必要な項目です。
• その他
残留リスクへの対応(例:安全標識の設置や作業者への周知徹底など)や、対策の実施期限、担当者などを記載します。
リスクアセスメントの書き方のポイント
リスクアセスメントの記録を作成する際は、労働者に安全を確保するという目的を達成するため、以下の点を意識しましょう。
• 作業や危険はできるだけ具体的に書く
• 誰が、何をして、どんな危険が起こるのかなど、原因と結果を明確につなげて記述する
• リスク評価は定量化すると対策の優先順位がつけやすい
リスクアセスメントの記録を作成する際は、作業や危険はできるだけ具体的に書きましょう。
誰が、何をして、どんな危険が起こるのかなど、原因と結果を明確につなげて記述することで、曖昧さをなくします。さらに、リスク評価は定量化すると対策の優先順位がつけやすいのも特徴の1つです。このプロセスを通じて、労働者の安全意識も向上します。
【参考】 「リスクアセスメントの実施支援システム - 職場のあんぜんサイト」 (厚生労働省)
製造業におけるリスクアセスメントの書き方例
ここでは、製造業の現場を想定したリスクアセスメントの記載例を紹介します。
| 作業名・設備名 | 危険性・有害性(災害の種類) | リスクの見積り(現時点) | リスク低減策 | 低減後のリスク |
| 電動フォークリフトによる運搬作業(倉庫A) | フォークリフトと作業者の接触による轢過 | 12点(大) | 作業通路と歩行通路の明確な分離・可視化、速度制限標識の設置 | 4点(小) |
| プレス機(製品X成型)の金型交換作業 | 金型の落下による作業者の下肢切断 | 16点(特大) | 交換手順書の作成・周知、補助具の導入、二人作業の義務付け | 6点(中) |
| 化学物質(洗浄液Y)の計量・投入 | 洗浄液の飛散による皮膚炎や目の損傷 | 9点(中) | 局所排気装置の点検記録義務化、防護眼鏡・耐薬手袋の常時着用 | 3点(小) |
上記の事例で想定されている危険は、機械との接触や落下、化学物質による健康被害といった製造現場で一般に発生しやすい災害です。
現状のリスクレベルが高い場合(例:フォークリフトの12点やプレス機の16点)は、最優先で対策が講じられています。
リスク低減のために行われた対策は、「通路の分離(本質的・工学的対策)」や「手順書の作成(管理的対策)」、「保護具の着用」など、原則に従って検討しましょう。
その結果、対策実施後のリスクレベルは大幅に変化し、許容できる範囲に低減されていることが確認できます。
i-Reporterでリスクアセスメント!書き方の負担を軽減し、安全を管理
リスクアセスメントは、職場の安全を確保するために必要な活動です。しかし、その効果は作成した記録をいかに管理・活用し、継続的に見直せるかが重要となります。
紙のシートで運用していると、「書類の保管や共有が大変」「過去の履歴を探しにくい」「対策の進捗が追いづらい」といった課題に直面しがちです。
現場帳票システム「i-Reporter」は、リスクアセスメント管理全体の効率を向上させることが可能なソリューションで、使い慣れたExcelのリスクアセスメントシートを、そのままデジタル化できます。導入により、安全に関する情報を効率的に扱えるようになるでしょう。
現場で撮影した写真を直接貼り付けたり、過去の対策履歴をその場で参照したりできる機能は、記録・報告・共有がペーパーレスで行えるため、担当者の負担を大幅に軽減し、リスク管理の質を高めます。ぜひ、この機会にぜひご検討ください。