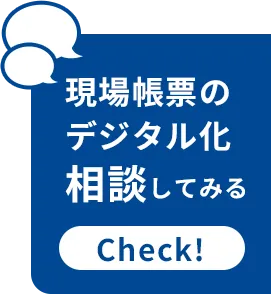SPC管理とは?目的やSQCとの違い、基本的な手順を紹介
目次
製造業の品質管理において、「不良品を減らしたい」「安定した品質を維持したい」という課題は常に付きまといます。
その解決に不可欠な手法として、長年にわたり重要視されてきたのが「SPC管理(統計的工程管理)」です。
SPC管理は、勘や経験ではなく統計的な手法を使用し、製造プロセスに潜むばらつきや異常を早期に検出する仕組みになります。
本記事では、製造業の品質管理担当者に向けて、SPC管理の本質を理解できるよう、目的やSQCとの違い、実践に役立つ基本的な手順まで徹底解説します。ぜひ参考にしてみてください。
SPC(統計的工程管理)とは
SPC(Statistical Process Control)は、「統計的工程管理」を意味する用語です。
SPCは、統計的な手法を活用して工程内の品質を監視・改善する仕組みであり、製造プロセスの安定化に不可欠な手法として知られています。
SPC管理が着目する「2種類のばらつき」
SPC管理を理解する上で重要なのが、品質のばらつきには「偶然原因」と「異常原因」の2種類があるという考え方です。
偶然原因は管理された安定した工程の中でも避けられません。自然でランダムなばらつきで、多数の軽微な要因(気温の微細な変化など)が複合的に絡み合って発生するもので、統計的な管理状態にあれば許容されます。
異常原因は突発的に発生する、特定の原因による大きなばらつきで、機械の故障や材料ロットの変更といった原因を特定し、取り除くべきものです。
SPC管理の目的は、管理図を用いてこの2つの原因を統計的に見分けることです。異常の発生を早期に発見・指摘することで、不良品の発生を未然に防げます。
SPC管理の目的
前述した通り、SPC管理の目的は、管理図を用いてこの2つの原因を統計的に見分けて異常の発生を早期に発見・指摘することにあります。
そしてSPC管理の導入は、単なる品質管理に留まらず、企業の経営にも以下のようなメリットをもたらします。
・コスト削減
・品質の安定化
・生産性の向上
・データに基づく意思決定ができる
コスト削減は、不良品の削減により、手戻り作業や再検査、廃棄にかかるコストを大幅に削ることができます。
また、品質が安定化すれば、一貫した品質の製品を製造できるようになり、顧客満足度の向上にも貢献します。
さらに、生産性の向上もメリットとして挙げられ、工程の無駄がなくなり、生産効率が向上するでしょう。異常が発生する前に対処できるため、ライン停止の時間も減らすことが可能です。
そして、データに基づく意思決定ができるようになり、勘や経験に頼るのではなく、統計データにもとづいた客観的で的確な改善活動が可能になります。
SPCとSQCとの違い
品質管理の分野では、「SPC」と「SQC」という言葉が頻繁に登場します。SPCとSQCの関係と違いを理解することは、品質管理の全体像を把握する上で重要です。
SQC(統計的品質管理)とは?
SQC(Statistical Quality Control)は、統計学的な手法を用いて、製品やサービスの品質を管理する活動全体を指す大きな概念です。
単に製造工程だけでなく、開発から出荷、サービスに至るまで、品質に関わるすべての段階を対象とします。
具体的には、抜き取り検査や実験計画法といった手法を駆使し、完成品の品質が事前に定められた規格を確実に満たしているかを評価・保証します。
この活動は、データに基づき品質の現状を可視化し、客観的な判断を可能にすることで、企業の信頼性と顧客満足度の向上に貢献するでしょう。
SQCにおけるSPCの位置づけ
SPCは、より大きな概念であるSQC(統計的品質管理)の一部です。
SQCが完成品の抜き取り検査や出荷前の評価といった製造後の品質管理活動の全般を担うのに対し、SPCは役割が異なります。
SPCは「製造工程のリアルタイム監視による予防」に特化しており、製造の最中にデータを収集・分析することで異常の兆候を捉えます。
そのため、SPCはSQCの中でも特に工程の安定化を図るための手法であり、不良品が出るのを未然に防ぐという予防的視点で重要なポイントです。
| 項目 | SPC(統計的工程管理) | SQC(統計的品質管理) |
| 対象 | 製造プロセス | 完成品や中間製品を含む品質全般 |
| 目的 | 製造工程を安定させることで、品質のばらつきや不良品を防ぐ(予防) | 製品の品質が基準を満たしているか評価し、保証する |
| 手法 | 管理図(コントロールチャート)で工程を監視 | 抜き取り検査、統計的分析(パレート図、特性要因図など) |
| タイミング | 製造中(リアルタイム監視) | 製造後や出荷前 |
※管理図とは:製造工程の品質特性の値を時系列に記録し、統計的に計算された管理限界線と比較するグラフです。工程が統計的に管理された状態にあるかを視覚的に判断するために使用されます。
※Cpkとは:工程能力指数の一つで、プロセスが規格限界線の中でどれだけの余裕を持って製品を製造できるかを数値で評価する指標です。
SPCやSQCを支える分析手法「QC7つ道具」
SQC全体の活動において、データの分析や問題の可視化に用いられるのが「QC7つ道具」です。
QC7つ道具は、品質管理の基本的な手法であり、製造現場で問題解決や現状把握を行う上で非常に役立ちます。複雑な事象から本質的な情報を抽出し、客観的な改善活動を促進するために設計されています。
その中でもSPCでは特に「管理図」をメインツールとして工程を監視するのが特徴です。管理図で異常が検知された際には、その異常の根本原因を深掘りするため、「特性要因図」(原因と結果の関係を整理)や「パレート図」(重要な問題を特定)などが効果的に使用されます。
QC7つ道具の効果的な活用は、統計的品質管理活動全体の成功に不可欠です。これらは、製造や事務など幅広い業務で活用できる基本的な分析ツールであり、データに基づく意思決定の質を高めます。
QC7つ道具について詳しく知りたい方は、下記記事も参考にしてください。
QC7つ道具とは?特徴や活用のメリット、ツールを使うときのポイント
SPC管理の基本的な手順
SPC管理は、製造プロセスの継続的な改善を図るための体系的な手法です。ここでは、SPC管理を実践する上での重要な4つのステップを解説します。
Step1. 管理対象の選定とデータの収集
製品品質に最も影響を与える重要な管理項目(寸法、重量、温度など)を特定し、項目のデータを継続的に測定し、記録する必要があります。
データ収集の段階では、チェックシート(QC7つ道具の一つ)などを用いて、正確なデータを効率的に集めることが重要です。
Step2. 管理図の作成と監視
収集したデータを管理図に記入し、工程が安定しているかを視覚的に監視しましょう。SPC管理傾向管理も重要な役割を果たします。
管理図は、データの種類によってXbar-R管理図などいくつかの種類を使い分ける必要があります。
工程に「異常原因」によるばらつきが発生していないかは、「ウェスタン・エレクトリック社の8つのルール」といった異常判定ルールを用いて客観的に判断します。
ウェスタン・エレクトリック社の8つの異常判定ルールとは、管理限界線の中で「統計的に異常」と判断するための視覚的基準を指します。具体的にデータが一方向に偏っている場合や、急激に変動している場合など、8つの視点から異常を識別します。
「管理限界線」と「規格限界線」の違い
SPC管理を正しく運用する上で、以下2つを混同しないことが重要です。
• 管理限界線
• 規格限界線
管理限界線は、工程データから統計的に計算される線(UCL:管理上限線、LCL:管理下限線)で、工程が「統計的に安定」しているかを判断する基準です。SPC管理sigmaを使って設定されます。
一方、規格限界線は、設計仕様や顧客要求によって定められる製品品質の許容範囲(USL:規格上限、LSL:規格下限)で、製品が「合格品かどうか」を判断する基準となります。
Step3.工程能力の評価
管理図で工程の安定化を確認した後、その工程が「製品規格を満たす能力」を持っているかを工程能力指数(Cp,Cpk)で定量的に評価します。
Cp(工程能力指数)は、工程のばらつきが規格範囲全体に対してどの程度収まっているかを示す指標です。
Cpは、プロセスの中心が規格の中心と一致している前提で評価されます。一方Cpk(工程能力指数)は、Cpに加え、プロセスの中心が規格中心からどの程度ずれているかを考慮した指標です。
工程の中心が規格から外れている場合でも、実際の能力を評価できるため、実用上非常に重要な指標になります。
Step4. 異常原因の特定と改善
管理図で異常が検知されたり、工程能力が低いと判断されたりした場合、根本原因を特定し、改善策を実行します。
原因分析の際には特性要因図(フィッシュボーン図)やパレート図といったQC7つ道具が用いられることがほとんどです。
異常原因を特定し、それを取り除くことで、工程を統計的に管理された状態に戻し、品質の安定化を図ります。
SPC管理を成功に導くデータ収集の鍵
SPC管理は、製造工程を安定させ、品質を向上させるために効果的な手法です。しかし、その分析結果は現場で収集されるデータの品質に依存します。
SPC管理の効果を最大限に引き出すためには、現場からリアルタイムで正確なデータを収集する仕組みが不可欠です。
手書きの記録やExcelへの転記作業では、ヒューマンエラーやタイムラグが発生しやすく、管理図や分析の信頼性を損なう可能性があります。
現場帳票システム「i-Reporter」なら、タブレットやスマートフォンで測定値を直接入力可能です。SPC管理システムを導入することで、転記ミスや報告の遅れを防げます。また、写真も記録できるため、異常発生時の状況も正確に共有でき、迅速な原因究明につながります。
SPC管理の基盤となるデータ収集を効率化することで、品質管理活動全体を強力に支援します。この機会に現場帳票システムi-Reporterの導入を検討してみてはいかがでしょうか。